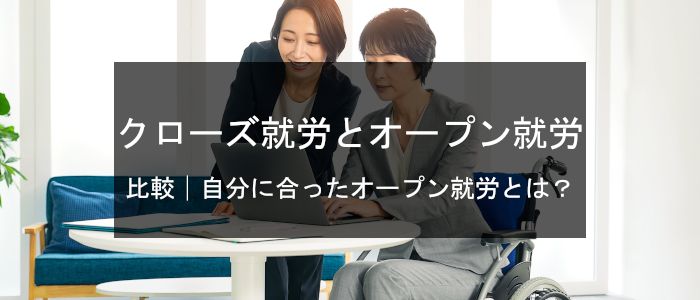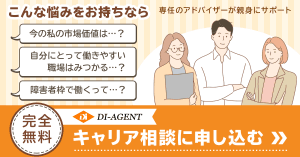障害を持ちながら働く上で、就業先にご自身の障害を伝えるか迷っている方も多いのではないでしょうか。
実際に、「障害があることを伝えたら就職が難しくなる」「今の職場では続けていけなくなってしまう」という悩みを抱えている方は少なくありません。
一般的に、障害があることを周囲に伝えずに働くことを「クローズ就労」、周囲に伝えた上で働くことを「オープン就労」と言います。
今回は、それぞれにどの様なメリット・デメリットがあるかを詳しく解説します。ご自身にとってどちらが合っているかを考えるうえでも、最後までお読みください。
クローズ就労とオープン就労とは

ここでは、クローズ就労とオープン就労の働き方についてご紹介します。
クローズ就労の概要
クローズ就労とは、周囲へ障害について公開しない働き方のことで、一般採用枠での就労を指します。「障害を隠していても問題はないのか」といった疑問をもつ方もいらっしゃいますが、就労時に障害を開示することは義務ではなく、開示せずに就労を続けることも問題ではありません。
しかし、当然ながら障害への配慮を受けることができないため、注意が必要です。
オープン就労の概要
オープン就労は、周囲へ障害について公開した働き方のこと。一緒に働く社員や上司へ、自分が障害者であることを伝え、配慮(サポート)を受けながら就労することを指します。
障害についてオープンにする場合、どこからどこまでを伝えていいものか迷う方もいらっしゃいますが、伝えたくないことまで話す必要はありません。
オープン就労で働く場合は、一般枠と障害者枠のいずれかから求人を探す仕組みです。つまり、障害があるからといって雇用枠が限定されることはなく、いわゆる健常者と比べて同等、またはそれ以上の働き・成果が期待できる人材と判断されれば、一般枠でも働くことは可能です。
クローズ就労とオープン就労との違い
クローズ就労とオープン就労の違いは、大きく分けて2つあります。
- 障害の公開・非公開
- 求人の種類が変わる
それぞれ、障害を周囲に伝えるかどうかが異なり、それにともなって求人の種類も異なります。
たとえば、「障害を抱えていても、業務には影響がなく周囲に知っておいてもらう必要がない」といった場合であればクローズ就労を選び、一般採用枠から求人を選ぶのも一つの手段です。
もし、「障害を抱えていて、自分ではできないことも多い。サポートを受けながら働きたい」と考えるなら、オープン就労の障害者枠から求人を選ぶとよいでしょう。
それぞれ、どちらがよいか悪いかは一切なく、どちらを選んでも問題ありません。大切なのは、「自分らしく働ける就労スタイルとはなにか」「どちらを選べば安心して長く働き続けられるか」です。
クローズ就労のメリット・デメリット

クローズ就労には、メリットとデメリットの両方があります。障害について公開せず、一般採用枠で働くうえで、メリット・デメリットを把握し働き方を考慮するのは、非常に重要です。
クローズ就労のメリット・デメリットは、以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 1. 求人数が豊富: 一般採用枠で職種・業種が幅広い | 1. 障害を隠すことで働きにくさを感じる: 発覚への懸念がストレスに |
| 2. キャリアアップを目指しやすい: 専門職や管理職の求人が多い | 2. 障害への配慮(サポート)が受けられない:業務遂行に支障が出る可能性 |
| 3. 一般就労と相違なく働ける: 過度な気遣いを避けられる | 3. 支援機関と就職先が連携しておらず、サポートが受けられない:職場での悩みを抱え込む恐れ |
以下で、メリット・デメリットについて具体的に解説します。
メリット1.求人数が豊富
一つめのメリットは、求人数が豊富な点です。クローズ就労は一般採用枠であることから、豊富な求人のなかから自分にあった求人をみつけやすいメリットがあります。
オープン就労の障害者枠と比べると職種・業種が幅広いので、自身にあった働き方を見つけられます。「配慮(サポート)を受けなくても問題なく働ける」といった方には大きなメリットと言えるでしょう。
メリット2.キャリアアップを目指しやすい
二つめのメリットは、キャリアアップを目指しやすい点です。一般採用枠には、専門職や管理職の求人など裁量的な働き方やパフォーマンスを求める求人、幅広く業務を担当する総合職の求人が豊富にあります。
これらに応募し、就労できれば、経験を活かし、キャリアアップを目指して働くことが可能です。
配慮やサポートのなかには、障害をお持ちの方への思いやりから、就労時間や業務内容などにある程度の制限を設ける会社も少なくありません。
クローズ就労を選ぶ方の多くは、障害への配慮(サポート)を受けない・受ける必要がないと自身で判断した方なので、配慮やサポートによる制限をなくし、一般就労によってキャリアアップを目指しながら働くことができます。
メリット3.一般就労と相違なく働ける
三つめのメリットは一般就労と相違なく働ける点です。クローズ就労は一般採用枠に応募し就労すること。そのため、以下のように考える方にはおすすめの働き方です。
- とくに配慮は必要ない
- 気を遣われるのが嫌
良くも悪くも、障害者扱いされないので、周囲に必要以上に気を遣わせずに働きたい方にはメリットと言えるでしょう。
デメリット1.障害を隠すことで働きにくさを感じる
クローズ就労には3つのデメリットもあります。一つめは障害を隠すことで働きにくさを感じる点。
障害を公表しないので、「いつか障害が発覚するのでは」といった不安を抱えながら働く方もいます。
しかし、障害を隠していたからといって、企業から解雇されることはなく、またそのようなことはあってはならないことになっています。
障害の重さは人によって異なります。障害をお持ちで配慮がなくても働ける方は、隠すことに後ろめたさを感じる必要はないので安心しましょう。
ただし、休職期間や前職の理由が障害によるものだった場合は、正直に伝えなければなりません。嘘の理由や誤った休職期間を伝えると、詐称となり解雇される可能性があるので注意しましょう。
デメリット2.障害への配慮(サポート)が受けられない
二つめのデメリットは、障害への配慮(サポート)が受けられない点です。企業や配属する部署、一緒に働く社員には障害を公開しない働き方なので、当然ながら配慮(サポート)は受けられません。
もし、業務についていけず、周囲から見て仕事が遅いと判断されると、やがて仕事に対してストレスを抱える可能性があります。
クローズ就労を選ぶときは、障害について主治医と相談してから決めるのが望ましいでしょう。
デメリット3.支援機関と就職先が連携しておらず、サポートが受けられない
三つめのデメリットは、支援機関と就職先が連携していないために、支援機関と職場間のサポートが受けられない可能性がある点です。
オープン就労だと、障害についてオープンにしているので、支援機関を利用していた方は定着支援等のサポートが受けられる可能性があります。
しかし、クローズ就労は障害を公開していないため、支援機関と職場間のサポートが受けられず、業務における悩みを抱え込んでしまったり、職場の人間関係に悩んだりする恐れがあります。
クローズ就労は、自身の働き方や目的において「障害は公開する必要がない」と判断したうえでの働き方です。クローズ就労を選ぶときは、この点を視野に入れながら応募するのが望ましいでしょう。
なお、自分にはどちらが合っているのか判断に迷う方もいらっしゃるでしょう。DIエージェントは障害者雇用支援実績が豊富で、これまでに7,500名以上の方を支援して参りました。「自分はどちらが合っているんだろう」「それぞれの違いについてもう少し知りたい」といった方は、以下バナーからいつでもお気軽にご相談ください。
オープン就労のメリット・デメリット

障害のことを周囲に公開して働くオープン就労にも、メリットとデメリット両方あります。オープン就労のメリット・デメリットの概要は、以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 1. 障害への配慮(サポート)を申し出やすい:服薬時間や通院休暇の相談がしやすい | 1. 求人数が少ない::障害者枠は一般枠より限定的 |
| 2. 通院・投薬について理解がある:定期的な受診を前提とした働き方が可能 | 2. 職種の選択肢が限られる:すべての業種でオープン就労が可能なわけではない |
| 3. 障害のことを隠して働く罪悪感がない:障害を隠さず自分らしく働ける |
以下で、オープン就労のメリット・デメリットについて詳しく解説します。しっかりと把握し、クローズ・オープンのどちらで働くのが自分に合っているのか、考えてみてください。
メリット1.障害への配慮(サポート)を申し出やすい
一つめのメリットは、障害への配慮(サポート)を申し出やすい点です。障害を周囲に公開していることから、服薬の時間や受診による休暇について申し出やすくなります。
さらに、業務中に症状が出た場合でも、配慮(サポート)を受けながら取り組めるので安心して働き続けられます。
メリット2.通院・投薬について理解がある
二つめのメリットは、通院・投薬について理解がある点です。障害について公開しているので、通院を前提とした取り組み方で働けます。
投薬がある場合は定期的な受診がともなうので、平日のどこかで仕事を休み、医師に診てもらう必要があります。通院や投薬がある方にとっては、安心して働ける点は大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3.障害のことを隠して働く罪悪感がない
三つめのメリットは、障害のことを隠さずに働くので、罪悪感がない点です。第一に、障害を持つことに責められる理由はありません。しかし、障害があることを公開せずに働くと、「周囲に隠し事をしているようだ……」と罪悪感を持つ方も少なくありません。
オープン就労は、あらかじめ障害について公開しているので、心苦しさを感じることなく自分らしく働けます。
デメリット1.求人数が少ない
一方、オープン就労には2つのデメリットがあります。一つめは求人数が少ない点です。オープン就労の割合として多くを占める障害者枠求人は、一般枠に比べて求人数は少なく、職種や業務内容が限定的な傾向があります。
一般枠の求人に障害をオープンにして応募することも可能ですが、障害への理解や配慮を前提としていない求人が多いため、選考のハードルは相応に高くなります。
結果として、オープン就労では選択肢がやや限られているのが現状です。
だからといって、無理にクローズ就労を選ぶ必要はなく、症状の経過や主治医との相談によって、オープン就労を視野に入れるのも手段の一つと言えるでしょう。
デメリット2.職種の選択肢が限られる
二つめのデメリットは、職種の選択肢が限られる点です。クローズ就労の一般採用枠に比べ、オープン就労は障害者雇用枠。
事務職や清掃職、データ入力作業などの職種が多く、キャリアアップを目指す方にとってはデメリットに感じられるでしょう。
とはいえ、投薬などによっては障害の症状が軽減し始め、問題なく働けるまでに改善する可能性もあります。
クローズ就労・オープン就労それぞれにはメリットがあり、障害をお持ちの方ひとりひとりにあわせて選べる方法です。
クローズ就労とオープン就労の定着率

クローズ就労とオープン就労の定着率には、求人の種類によって違いが見られます。2017年4月に独立行政法人 障害者職業総合センターから発表されたデータによると、求人の種類ごとの定着率は以下の通りです。
| 求人の種類 | 3ヶ月後定着率 | 1年後定着率 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型求人 | 88.0% | 67.2% |
| 障害者求人 | 86.9% | 70.4% |
| 一般求人(障害開示) | 69.3% | 49.9% |
| 一般求人(障害非開示) | 52.2% | 30.8% |
このデータから、障害者求人が最も高い定着率を示していることがわかります。ちなみに、就労継続支援A型とは、障害をお持ちの方と雇用契約を結び、働く機会を提供する福祉サービスです。
一方で、一般求人で障害を非開示にするクローズ就労の定着率が最も低くなっています。
なお、一般枠でも、オープン就労はクローズ就労よりも高い定着率を示しています。これは、職場での適切な配慮や支援が受けられることが要因の一つと考えられるでしょう。
引用元
障害者の就業状況等に関する調査研究|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
一般枠でオープン就労を目指す際のポイント

一般枠でのオープン就労は、より幅広い職種や高い給与水準を目指せる可能性がある一方で、障害への配慮が十分でない環境に直面する可能性もあります。そのため、自身の状況を適切に管理し、職場環境に適応するための準備が重要です。
ここからは、一般枠でオープン就労を成功させるためのポイントを見ていきましょう。
引用元
就労に向けて 求められるもの|国立障害者リハビリテーションセンター
1.健康管理と自身の特性の理解
一般枠でオープン就労を目指す上で、最も重要なポイントの一つが、健康管理と自身の特性の理解です。
日々の健康管理を徹底することで、予期せぬ病気や症状の悪化を防ぐことができます。また、自身の障害特性を深く理解することも不可欠です。
自身の特性の理解を深めることで、職場での自己管理がしやすくなるだけでなく、必要な際に上司や同僚に適切に説明し、理解や協力を得やすくなります。例えば、「騒がしい環境では集中力が低下するため、静かな場所で作業させていただけると助かります」といった具体的な配慮の要請ができるようになるでしょう。
2.生活サイクルを整える
安定した生活サイクルを確立することも重要です。規則正しい生活リズムを維持することで、遅刻や欠勤のリスクを大幅に減らすことができ、職場での信頼性を高めることにつながります。
また、安定した生活サイクルは、前述の健康管理にも直結します。十分な睡眠時間を確保することでストレス耐性が高まり、心身の健康維持に役立つでしょう。さらに、規則正しい生活は、服薬管理や定期的な運動の習慣化にも役立ちます。
3.労働習慣やビジネスマナーを把握する
障害の有無に関わらず、社会人として基本的な労働習慣やビジネスマナーを身につけることは不可欠です。職場での円滑なコミュニケーションや業務遂行の基盤となり、同僚や上司からの信頼を得る上で重要な要素となるからです。
時間厳守や適切な挨拶・電話やメールの応対方法・ビジネス文書の作成方法などのスキルを習得することで、職場での適応がスムーズになり、業務効率も向上するでしょう。
4.職業適性を知る
自身の職業適性も、あらかじめ知っておきましょう。職種や業務によって求められる能力や適性は大きく異なるため、自分の強みや弱み、興味関心を深く理解し、それらと職業要件とのマッチングを行うことが成功の鍵となります。
例えば、コミュニケーション能力が高い場合は営業職や接客業が適している可能性があり、細かい作業が得意な場合はデータ入力や品質管理などの業務が向いているかもしれません。
職業適性を知ることは、就職活動時のアピールポイントの明確化にもつながります。自身の強みや経験を具体的に説明できることで、面接時により説得力のある自己PRが可能となり、採用の可能性が高まるでしょう。
職業適性を知るためには、自己分析だけでなく、専門家のアドバイスを受けることも効果的です。
就職のサポートや相談などに応じてくれる支援機関

オープン就労・障害者雇用は、就労支援サービスを利用することができます。就職のサポートや相談などに応じてくれる支援機関について見ていきましょう。
ハローワーク
ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。窓口や施設に設置してある検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。
ハローワークには専門援助部門が設けられており、窓口には専門の相談員が配置され、障害をお持ちの方が就職活動をするための支援を行っています。
一般向けの求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗ってくれ、障害のある方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害をお持ちの方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。全都道府県に最低1カ所ずつ以上設置することが義務付けられています。
センターでは、直接就職先を紹介するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携しながら、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといった支援を実施しています。
障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。
引用元
障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、トレーニングと就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。
利用者にとって、事業所に通いながら就職に必要な知識や技術を獲得でき、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。
全国に3,300カ所以上あり、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障害をお持ちの方の仕事面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などと呼ばれることもあります。
なかぽつは、全国に337カ所(令和5年8月22日時点)設置されています。社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。
障害をお持ちの方への就職支援や助言のほか、事業所に対して障害者雇用に関する助言を行ったり、関係機関との連絡調整を実施したりしています。
引用元
障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省
令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧 (計 337センター)|厚生労働省
障害者向け転職エージェント
障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化した、転職エージェントもぜひ利用してください。
障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。
高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。
就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。
クローズとオープンとの違いについて押さえ、自分らしく働ける方を選ぼう

転職のゴールは「採用されること」ではなく「職場に定着できること」。その視点で、ご自身にとってどちらの働き方が合うかを考えることが重要です。
もし「できれば障害をオープンにして働きたいけど、選択肢が少なくて不安」とお悩みの方は、DIエージェントにご相談ください。障害をオープンにするからといって、給与やキャリアアップなどを諦める必要はありません。両方を実現できるように、可能性を最大限追求します。
経験豊富なキャリアアドバイザーが お一人おひとりの状況やご希望に合わせて適切なご提案をさせていただきます。
▼関連記事
・DIエージェントに懸ける思いを運営会社代表の小林が語ったインタビュー記事です。一歩踏み出す勇気が持てないという方はぜひご一読ください。
一人ひとりの可能性を最大限追求するエージェント 一歩踏み出す勇気を 【対談企画 株式会社ミライロ垣内俊哉 × 株式会社D&I小林鉄郎(後編)】
・障害者枠であっても、転職によってキャリアアップを実現する方法はあります。給与もキャリアも諦めたくない方はぜひご一読ください。
障害者枠でハイキャリアを目指す!転職エージェントが教える戦略的キャリアの築き方
・障害者枠であっても、転職によってキャリアアップを実現する方法はあります。給与もキャリアも諦めたくない方はぜひご一読ください。
「今は自分のペースで働けています」初の障害者枠での転職経験談 [転職成功事例 Vol.2]│DIエージェント

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。