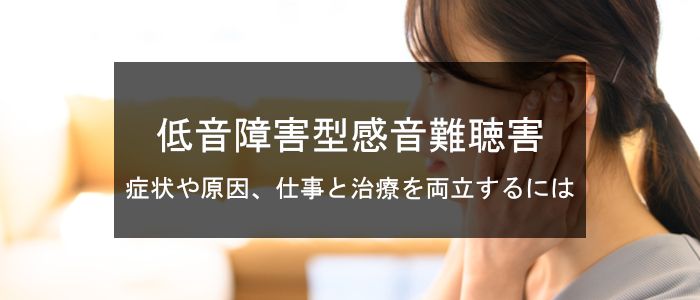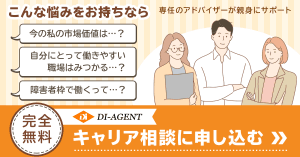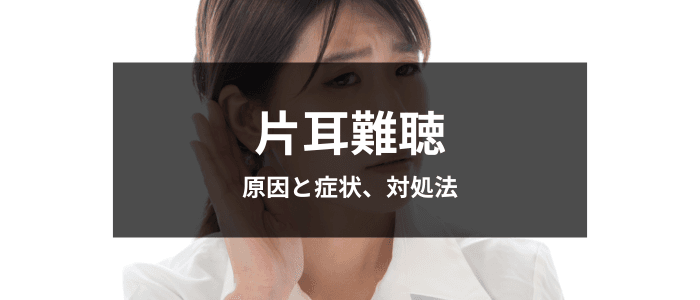低音障害型感音難聴は、突然発症し、再発の可能性もある耳の疾患です。耳が詰まったような感覚、低い音の耳鳴り、または自分の声が響くような症状に気づいた方もいるかもしれません。そこでこの記事では、低音障害型感音難聴の特徴と症状や仕事への影響と対応策について詳しく解説します。
仕事が忙しい中でこの疾患に直面した場合、治療を開始するタイミングや職場での対応、転職を検討する際のアプローチについても大切です。低音障害型感音難聴があっても、適切なサポートと理解のある職場環境であれば、安心して働くことが可能です。
低音障害型感音難聴とは?
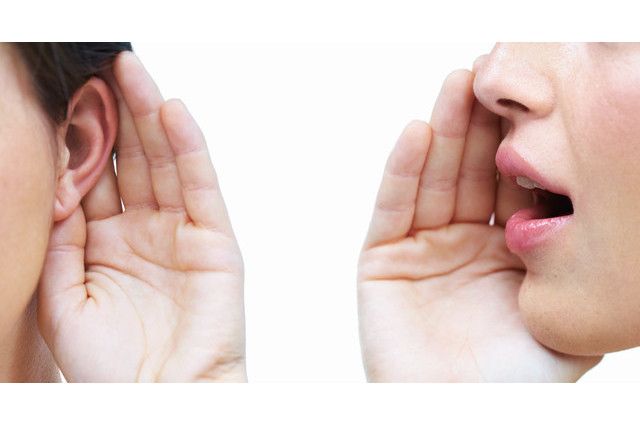
低音障害型感音難聴とは、低い周波数の音が聞き取りづらい難聴のこと。難聴には3つの種類があり、低音障害型感音難聴は感音性難聴に該当します。下記で3つの種類と低音障害型感音難聴の特徴について詳しく見ていきましょう。
耳が聞こえにくくなる難聴の1種|難聴は主に3種類ある
前述したように、低音障害型感音難聴は感音性難聴のひとつ。難聴の3種類とは、伝音性難聴(伝音難聴)・感音性難聴(感音難聴)・混合性難聴です。
伝音性難聴とは、外耳または中耳に問題が起きて聞こえづらくなってしまう難聴のこと。感音性難聴は、内耳から聴神経、もしくは脳に異常があって聞こえに支障が出る難聴のことです。
さらに、伝音性難聴と感音性難聴の両方の特徴を持つ場合、混合性難聴と呼ばれます。
突発性難聴との違いは?
低音障害型感音難聴と混同されやすい「突発性難聴」も、感音性難聴のひとつ。
低音障害型感音難聴では、耳の詰まり感があり、聞こえづらいのが低音のみに限られます。片耳でも両耳でも起こりやすいことに加え、再発を繰り返す可能性があることが特徴です。
それに対し、突発性難聴は急に聞こえにくくなるもので、聞こえにくい音域には個人差があります。片耳で起こりやすく、グルグルしためまいを伴うことも多いです。低音障害型感音難聴ではめまいは起こりません。
また、低音障害型感音難聴とは異なり、再発もしにくいといわれます。
メニエール病との違いは?
メニエール病とは、難聴や耳鳴りなどの聴覚障害を伴う断続的なめまい発作のこと。
低音障害型感音難聴と同じく感音性難聴のひとつで、初期には低音域の聞こえづらさを覚え、進行すると中~高音域にも障害が進行するとされています。また、週に数回や年に数回など頻度には個人差がありますが、慢性化しやすい病気です。
なお、メニエール病が軽くなると回転性めまいがなくなり、低音障害型感音難聴とほぼ同じ状態になります。
引用元
「ストレスが引き金になるメニエル病とは…」|日本医師会
低音障害型感音難聴は再発することも?|特徴から原因まで探ろう

前述したように、低音障害型感音難聴は、一度発症すると再発することもある病気です。ここからは、低音障害型感音難聴のその他の特徴や原因、予防策を見ていきましょう。
低音障害型感音難聴の主な特徴
低音障害型感音難聴は、あるとき突然起きるため、「急性低音障害型感音難聴」ともいいます。正常な聴力は0~24デシベルとされますが、低音障害型感音難聴の場合は26~40デシベルと、聴力レベルは軽度の難聴です。
対面での会話では大きな問題はない一方、離れた場所からの呼びかけには気づきにくい・騒がしい場所での会話や大人数での会話がしづらいといった特徴があります。
低音障害型感音難聴の主な症状
低音障害型感音難聴の主な症状として、以下のようなものが見られます。
- 耳が詰まっている・耳に水が入っているような感覚がある
- 低い音が聞き取りにくい
- 自分の声が耳の中で響くように感じる
- 低い耳鳴りを感じる
当てはまる症状がある場合、低音障害型感音難聴の可能性があるかもしれません。なお、人間が聞き取れる周波数は、20~20,000ヘルツの間とされます。
低音障害型感音難聴の主な原因
内耳には、うず巻き状の「蝸牛(かぎゅう)」という管があります。蝸牛の中に音を脳に伝える「有毛細胞」が存在し、周りをリンパ液が満たしている状態です。
低音障害型感音難聴は、このリンパ液が排出されずにたまり過ぎ、有毛細胞が圧迫されて機能しにくくなることが原因とされています。ストレス・睡眠不足・疲労などによって自律神経のバランスが崩れると、起こりやすくなるようです。
低音障害型感音難聴は再発する可能性も?日頃からの予防を
低音障害型感音難聴は、一度よくなっても再発する可能性があります。再発しないようにするためには、予防が重要です。ストレスや疲労をためない・よく眠る・バランスの取れた食事でしっかり栄養をとることを心がけましょう。
低音障害型感音難聴を発症してしまったら?|仕事は休む?

低音障害型感音難聴を発症したら、少しでも早く病院を受診し、治療を受けることが大切です。
仕事が忙しい方は、ついつい病院に行くことを後回しにしてしまいがち。しかし、治療を始めるのが遅れれば遅れるほど、治りが悪くなったり重症化したりする可能性が高いといわれます。
また、通院や治療をすると仕事に影響が出る可能性がありますが、職場の方々に相談し、できることなら仕事を休んで治療に専念したほうがよいでしょう。どうしても休めない場合は、対応できる仕事の範囲や環境について周りの方々の協力を得ましょう。
仕事と治療を両立するためのコツ

低音障害型感音難聴と仕事を両立するためには、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。ここからは、仕事と治療を両立するためのコツについて見ていきましょう。
1. 勤務先に相談する
職場でのサポートは、仕事と治療を両立する上で非常に重要です。勤務先に自分の状況をオープンに伝え、必要な配慮や支援を求めましょう。
特に、社内カウンセラーや産業医が所属している会社では、専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。具体的には、治療のスケジュールや必要な休暇、職務内容の調整などについて相談することが効果的です。
また、勤務先の理解と協力が得られることで、ストレスを減らし、仕事の効率を向上させることができます。例えば、定期的な健康診断や、職場でのリラックススペースの提供などです。
2. 環境を整える
低音障害型感音難聴の症状などを相談して周囲の理解を得たら、自分からも必要な配慮を伝えることが重要です。例えば、会議中の音量調整や、個別のミーティングルームの使用など、具体的な要求を伝えることで、より快適な職場環境を作り出すことができるでしょう。
周囲に自分の要望を伝えることで、理解を得るだけではなく、必要な配慮をしてもらうことも可能になります。職場でのストレスを減らすことができれば、より働きやすくなるでしょう。
3. 補助ツールを使用する
さまざまな補助ツールを活用すれば、低音障害型感音難聴の症状を軽減することができます。補聴器や文字起こしソフト、ノイズキャンセリングイヤホンなど、症状に合わせて最適なツールを選び、日常の業務に取り入れることが効果的です。
こういった補助ツールは、コミュニケーションをスムーズにし、仕事の効率を向上させるのに役立つでしょう。
例えば、補聴器は会話を聞き取りやすくし、文字起こしソフトは会議や電話でのコミュニケーションをサポートします。また、ノイズキャンセリングヘッドフォンは雑音を減らし、集中力を高められます。各ツールの特徴と使用方法を理解して、最適なツールを選択しましょう。
4. 仕事を変える
どうしても業務内容や職場環境が自分に合わなかったり、周囲の理解を得られなかったりする場合は、転職を検討することも一つの選択肢です。新しい職場では、より理解とサポートのある環境で働くことが可能になるかもしれません。
転職の際には、自分の要望と期待を明確にし、適切な職務を見つけるためのアプローチをすることが重要です。例えば、障害者雇用の促進を目指す企業や、テレワークが可能な職場など、自分に合った環境を探すことが効果的です。
また、転職前に現在の職場での経験やスキルを再評価し、自己PRを強化することも重要です。転職を通じて、より満足感の高い職業生活を送ることができるようになるかもしれません。
低音障害型感音難聴をお持ちの方が向いている仕事とは?

低音障害型感音難聴の方にはどんな仕事が向いているのでしょうか。以下に例を挙げるので、参考にしてみてください。
- 文字入力がメインになる事務職
- 自分のペースで進められる作業系の仕事
- コミュニケーションが必要でも音声認識ツール・手話・筆談などでやりとりができる職場
- 障害者雇用に力を入れている、あるいはすでに障害を持つ方の採用を行っており障害への理解が深い職場
低音障害型感音難聴があっても、環境が整っていれば職種を限定する必要はありません。ただし、聞こえないと身に危険がある仕事や、平衡感覚を必要とする仕事などは向いていない可能性もあるので、転職を考える際は慎重に検討しましょう。
以下で、具体的な求人を紹介します。
文字入力がメインになる事務職
文字入力がメインになる事務職は、低音障害型感音難聴を持つ人が安心して働くことができる職種の一つです。このタイプの仕事では、主にパソコンを使用したデータ入力、文書作成、電子メールの対応などが中心となり、音声コミュニケーションの必要性が比較的低いです。
自分のペースで進められる作業系の仕事
自分のペースで進められる作業系の仕事は、低音障害型感音難聴を持つ人が自律的に働くことができる職種です。このタイプの仕事では、特定の時間制約や急ぎのタスクが少なく、個々の作業ペースに合わせて進めることができます。
コミュニケーションが必要でも音声認識ツール・手話・筆談などでやりとりができる職場
コミュニケーションが必要な職場でも、音声認識ツール、手話、筆談などを活用することで、低音障害型感音難聴を持つ人でもスムーズにやりとりができる職場があります。このタイプの職場では、最新のテクノロジーを活用してコミュニケーションのバリアを低減し、すべての従業員が平等に参加できる環境が整っていることが多いです。
難聴をお持ちの方の仕事探しはどうする?

ここからは、低音障害感音難聴をお持ちの方が転職活動をする際に、相談に乗って支援してくれるサービスを紹介していきます。
低音障害感音難聴ではありませんが、ぜひ下記の転職事例も参考にしてください。
ハローワーク
ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。窓口や施設に設置してある検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。
ハローワークには専門援助部門が設けられており、窓口には専門の相談員が配置され、障害をお持ちの方が就職活動をするための支援を行っています。
一般向けの求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗ってくれ、障害のある方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害をお持ちの方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。全都道府県に最低1カ所ずつ以上設置することが義務付けられています。
センターでは、直接就職先を紹介するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携しながら、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといった支援を実施しています。
障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。
引用元
障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、トレーニングと就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。
利用者にとって、事業所に通いながら就職に必要な知識や技術を獲得でき、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。
全国に3,300カ所以上あり、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障害をお持ちの方の仕事面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などと呼ばれることもあります。
なかぽつは、全国に337カ所(令和5年8月22日時点)設置されています。社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。
障害をお持ちの方への就職支援や助言のほか、事業所に対して障害者雇用に関する助言を行ったり、関係機関との連絡調整を実施したりしています。
障害者向け転職エージェント
障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化した、転職エージェントもぜひ利用してください。
障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。
高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。
就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。
難聴をお持ちの方でも仕事はいくらでもある!自身の障害と向き合うことが大切

低音障害型感音難聴は突然発症することがあり、再発のリスクも伴うため、症状を早期に把握し、適切に対応することが重要です。もし発症した場合、仕事を休むか、症状に配慮した職場を探すことが必要です。
具体的には、文字入力がメインとなる業務や自分のペースで進められる業務などがおすすめです。
また、障害者枠で働く場合、事前に症状を伝え、配慮をしっかりとすり合わせたうえで入社することが、安心して働くための鍵となります。筆談や手話での対応や、補助ツールの利用などが可能な環境であれば、より安定して働き続けられるでしょう。
DIエージェントでは、障害をお持ちの方一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくるために、就職・転職支援を提供しています。
「今の自分に無理のない働き方をしたい」「症状に理解のある環境で働きたい」というご希望をお持ちの方に対して、就職・転職についてのアドバイスや、ご希望に沿った障害者枠の求人紹介を行っております。ぜひ一度ご相談ください。
▼関連記事
・障害者手帳を取得することによって、様々なメリットがあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
障害者手帳とは?対象疾患・等級、 受けられるサービスなどもわかりやすく解説!【専門家監修】│DIエージェント
・障害を持ちながら生活収入を確保する方法について解説しています。以下の記事もあわせてご覧ください。
障害者の方の2つの収入源を解説|障害年金と障害者雇用について【社労士監修】 │DIエージェント
・聴覚障害のある方の転職については、下記ページを参考にしてみてください。
聴覚障害者の方の仕事について|仕事探しや働くうえでのヒントなど解説│DIエージェント

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。