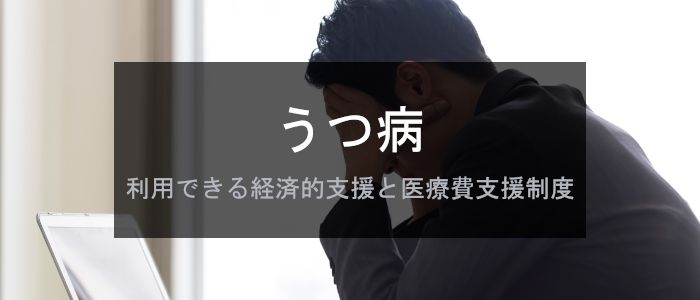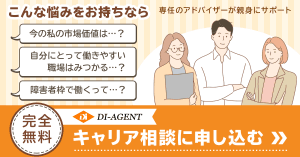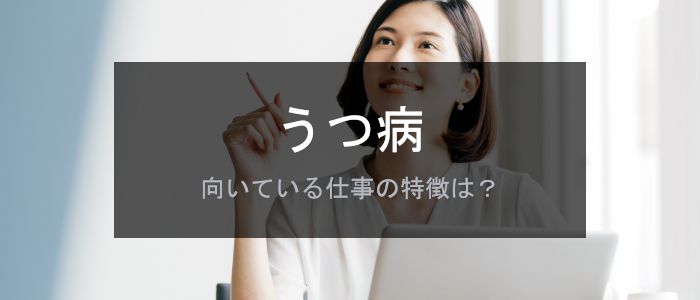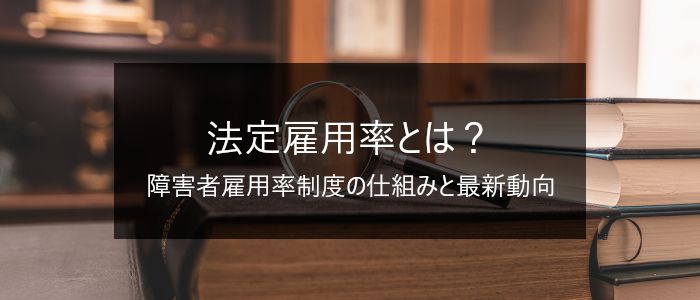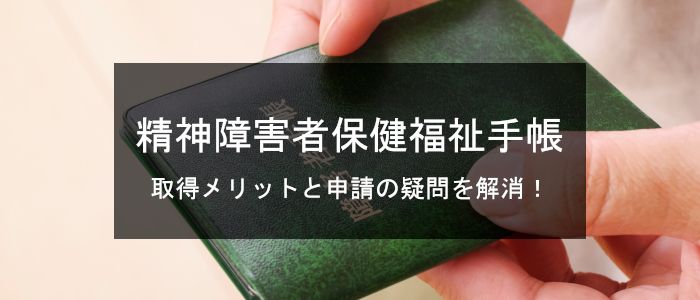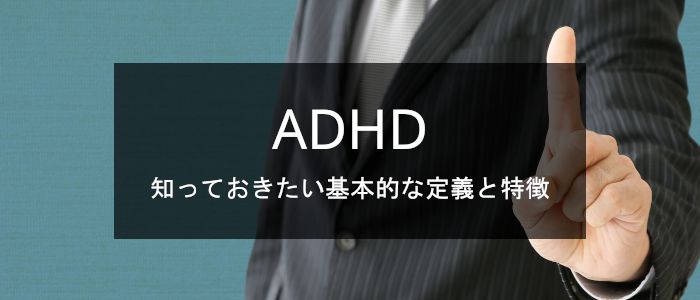うつ病は仕事や日常生活に支障をきたし、経済的な不安を抱える方も少なくありません。しかし、うつ病をお持ちの方が利用できる、さまざまな支援制度が存在します。
そこで今回は、うつ病に焦点を当て、うつ病をお持ちの方が利用できる経済的支援と医療費支援の制度を詳しく解説します。
傷病手当金や障害年金などの経済的支援・自立支援医療制度や重度心身障害者医療費助成制度などの医療費支援を活用することで、治療に専念しながら経済的負担を軽減できる可能性があります。
うつ病で仕事ができなくなったら退職しなければいけないの?
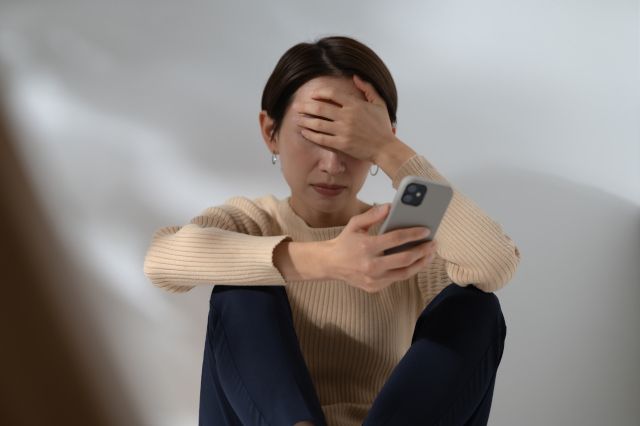
うつ病で仕事ができなくなった場合でも、即座に退職する必要はありません。多くの企業では、従業員の健康と福祉を重視し、休業制度を設けているからです。この制度を利用すれば、治療に専念しながら雇用を維持できる可能性があります。
まずは上司や人事に相談し、会社の方針や利用可能な選択肢について確認してみましょう。休業制度を利用することで、回復後に円滑に職場復帰できる可能性が高まります。
ただし、個人の状況や会社の規定によっては、退職が最善の選択肢となる場合もあるため、慎重に検討する必要があります。
休職前に確認しておきたいこと
休職を検討する際は、いくつかの重要な点を事前に確認しておくことが大切です。まず、休業期間の上限を把握しましょう。多くの企業では、就業規則に休職期間の上限が定められています。
次に、休職中の給与について確認が必要です。完全に無給となる場合もあれば、一部支給される場合もあります。
また、社会保険の扱いも重要なポイントです。健康保険や厚生年金の継続加入が可能かどうか、保険料の負担はどうなるのかを確認しましょう。
さらに、休職中の連絡方法や、復職のタイミングと手続きについても事前に把握しておくこと、スムーズな休職と復職が可能です。
うつ病の方が受けられる経済的支援5つを紹介

うつ病をお持ちの方々にとって、経済的な不安は大きな負担になってしまいます。しかし、日本にはさまざまな支援制度が存在します。
ここからは、うつ病をお持ちの方が利用できる、5つの主要な経済的支援制度を見ていきましょう。
1. 傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、十分な報酬が得られない被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。この制度は、健康保険に加入している労働者が利用できます。
申請をするには、医師の診断を受けてから必要書類を用意します。その後、勤務先を通じて、または直接加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請書を提出します。
引用元
全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
全国健康保険協会|傷病手当金の申請
傷病手当金が支給される要件とは?
傷病手当金の支給は、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養中の場合
- 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)(入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります)
- 休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合
- 4 日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した 3 日間は待期期間となり、4 日目から支給の対象になります)
2. 障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金制度です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
医師の診断書を取得し、必要書類を揃えて年金事務所に申請します。うつ病による障害も、一定の条件を満たせば障害年金の対象となる可能性があります。
引用元
日本年金機構|障害年金
日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金の受給要件は?
障害年金の受給要件は、障害基礎年金と障害厚生年金で若干異なります。
障害基礎年金の場合、主な要件は以下の通りです。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間中であること
- 障害の状態が、障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当していること
- 一定の保険料納付要件を満たしていること
障害厚生年金の場合は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日があることや、障害等級が1級から3級のいずれかに該当することなどが要件となります。
引用元
日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構|障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
3. 特別障害者手当
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給される手当です。この制度は、重度の障害のために必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減を目的としています。
申請先は、居住地の市区町村の福祉事務所です。
引用元
厚生労働省|特別障害者手当について
東京都福祉局|特別障害者手当(国制度)
特別障害者手当の支給要件は?
特別障害者手当の主な支給要件は、以下の通りです。
- 20歳以上であること
- 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
- 在宅で生活していること
また、所得制限があり、受給資格者や配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は、手当が支給されません。具体的な基準や申請手続きについては、居住地の市区町村窓口に相談してみてください。
4.失業保険
失業保険(雇用保険の失業等給付)は、失業中の生活を支えるための制度です。うつ病で退職した場合でも、一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。申請先は、最寄りのハローワークです。
受給には、原則として離職前2年間に12か月以上の被保険者期間があることなどの条件があります。また、受給期間や金額は、年齢や被保険者であった期間・離職理由によって異なります。
引用元
ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内
5. 生活保護
生活保護は、生活に困窮する人に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。うつ病で働けず、他の支援制度を利用しても生活が困難な場合の最後のセーフティネットです。申請は、居住地の福祉事務所で行います。
引用元
厚生労働省|生活保護制度
東京都福祉局|生活保護制度とはどのような制度ですか。|生活保護
生活保護の受給要件とは?
生活保護の受給要件は、世帯の収入が最低生活費を下回っていることが基本となります。ただし、利用可能な資産・能力・他の制度などをすべて活用することが前提です。
具体的には、以下の通りです。
- 預貯金や不動産などの資産を活用すること。
- 働ける場合は就労すること。
- 年金や手当など他の制度で受給できるものがあればそれらを利用すること。
- 親族からの援助を受けられる場合はそれを受けること。
これらの要件を満たしても、なお生活に困窮する場合に生活保護を受給できます。
うつ病の方が受けられる医療費支援3つを紹介
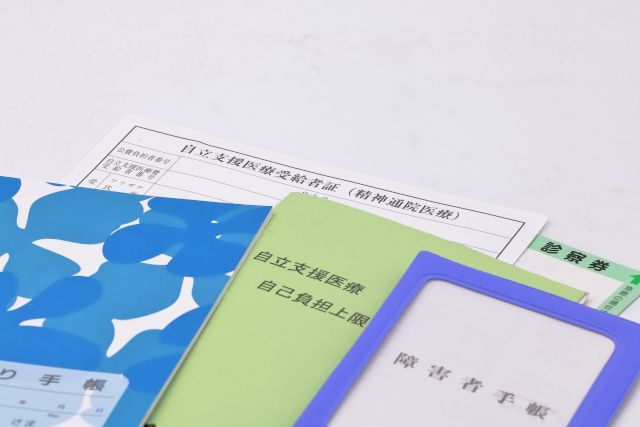
うつ病になったら、適切な治療を受けることが重要です。しかし、長期にわたる治療は経済的な負担を伴うことがあります。
そこで、うつ病患者の方々が利用できる3つの主要な医療費支援制度を紹介します。これらの制度を活用することで、経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えることができるでしょう。
1. 自立支援医療制度
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。うつ病などの精神疾患の治療に関しては、「精神通院医療」という区分で支援を受けることができます。
この制度を利用すると、通常3割の自己負担が1割に軽減されます。申請するには、まず主治医に相談し、必要な診断書を作成してもらいます。その後、居住地の市区町村窓口に申請書類を提出してください。審査を経て認定されると、自立支援医療受給者証が交付されます。
引用元
厚生労働省|自立支援医療制度の概要
東京都福祉局|自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療制度の対象者と対象医療とは?
自立支援医療制度の対象者は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害を有する方です。東京都を例に見ると、所得制限があり、世帯の区市町村民税が年23万5,000円以上の方は、原則として対象外です。ただし、高額治療継続者に該当する場合は、令和9年3月31日までの経過措置により対象となる可能性があります。
対象となる医療は、精神障害及びその治療に関連して生じた病態、または精神障害の症状に起因して生じた病態に対して、入院せずに行われる医療です。
これには、精神科での診察や投薬の他、デイケアなども含まれます。ただし、精神障害に起因するものとは考えにくい感染症・新生物・アレルギー(薬物副作用によるものを除く)・筋骨格系の疾患などは、一般的に対象外です。
2. 重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、心身に重度の障害を有する方の医療費を助成する制度です。東京都の例では、この制度は「重度心身障害者手当」として知られており、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により月額6万円が毎月支給されます。
申請は、居住地の区市町村窓口で必要書類を提出します。医師の診断書や障害者手帳、所得証明書などが必要です。
重度心身障害者手当の受給要件とは?
東京都の重度心身障害者手当の受給要件は、東京都の区域内にお住まいで、心身に東京都が定める重度の障害を有する方が対象となります。等級の基準は、以下の通りです。
- 1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
- 2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能を全廃したもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの
- 3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの
3. 精神障害者福祉手帳
精神障害者福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。この手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るための、さまざまな支援を受けるための基準となります。手帳の取得により、医療費の助成や税金の軽減、公共交通機関の運賃割引などの福祉サービスを受けられる可能性があります。
引用元
厚生労働省|障害者手帳について
こころの情報サイト|精神障害者保健福祉手帳
精神障害者福祉手帳の申請方法とは?
精神障害者福祉手帳の申請は、以下の流れで行います。
- 精神科医の診断を受け、診断書を作成してもらう。
- 診断書・写真・本人確認書類・マイナンバーに関する書類など、必要書類を揃える。
- 居住地の市区町村窓口に提出する。
申請から交付までは通常1〜3カ月程度かかります。なお、手帳は2年ごとに更新が必要で、更新時には再度診断書の提出が必要です。
支援を利用して療養中の不安を減らそう!

うつ病になっても、即座に退職する必要はありません。さらに、今回紹介した経済的支援や医療費支援制度を活用することで、療養中の経済的不安を軽減できる可能性があります。
自立支援医療制度や重度心身障害者医療費助成制度・精神障害者福祉手帳などの支援を適切に利用すれば、治療に専念できる環境を整えられるでしょう。
また、うつ病から回復した後の再就職に不安がある方は、ぜひDIエージェントへご相談ください。DIエージェントでは、うつ病からの回復者の方に寄り添い、適切な情報提供やご希望に沿った求人紹介を行っています。一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供し、スムーズな社会復帰をお手伝いいたします。
▼関連記事
うつ病の方の休職や復職について解説しています。
うつ病だと仕事は休めない?休職する方法や利用できる制度・手当を解説 | 障害者転職・就職のDIエージェント
今回の記事でも紹介した傷病手当金について掘り下げています。
働く人のための「休職」「傷病手当金」ガイド|人には聞けない疑問にもお答えします【障害分野にも詳しい社労士監修】

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。