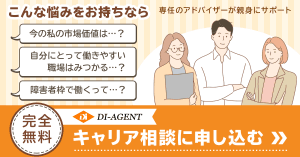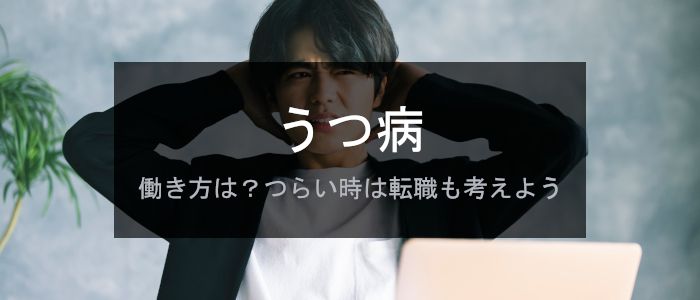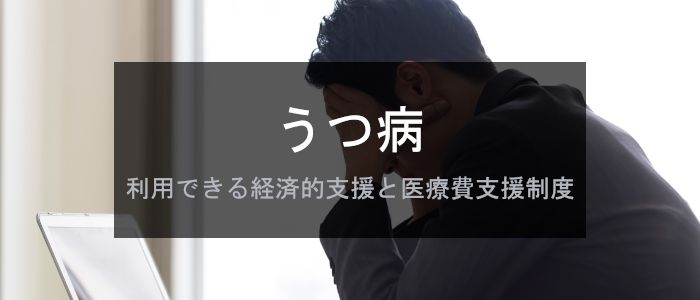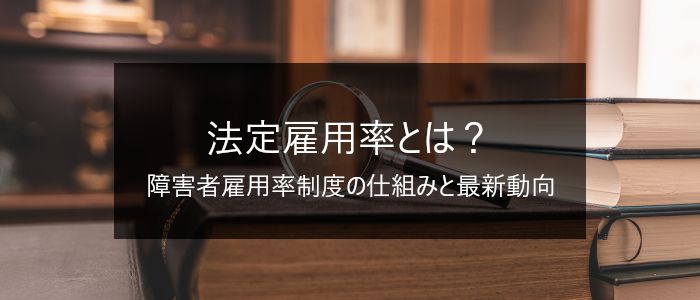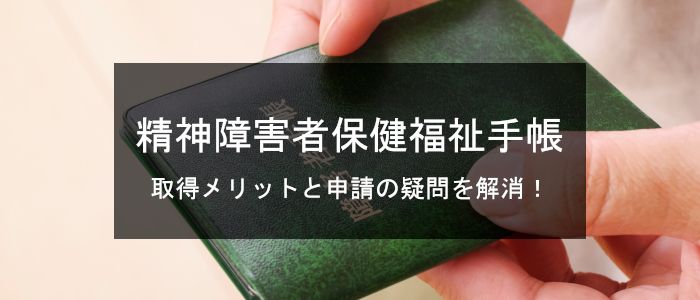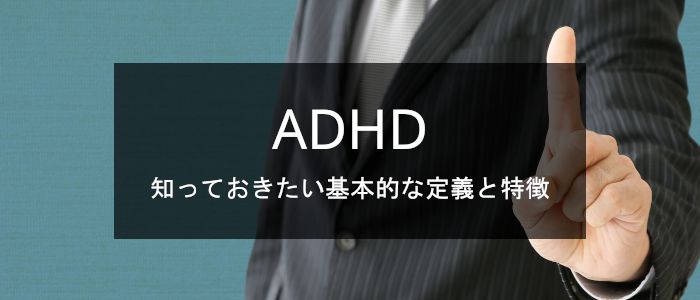うつ病は、仕事を続けることが困難になる場合があります。そのような状況で退職を考えている方にとって、どのように会社に伝えるべきか、退職までの手順はどのようなものかという疑問は切実なものでしょう。
そこで今回は、うつ病による退職を考えている方に向けて、退職の伝え方や退職までの流れを解説します。適切な方法で退職を伝えることは、自身の心身の負担を軽減するだけでなく、円滑な退職手続きにもつながります。
また、退職後に受けられるサポートや再就職に利用できる、支援機関も紹介します。
うつ病で退職するときの伝え方とは?
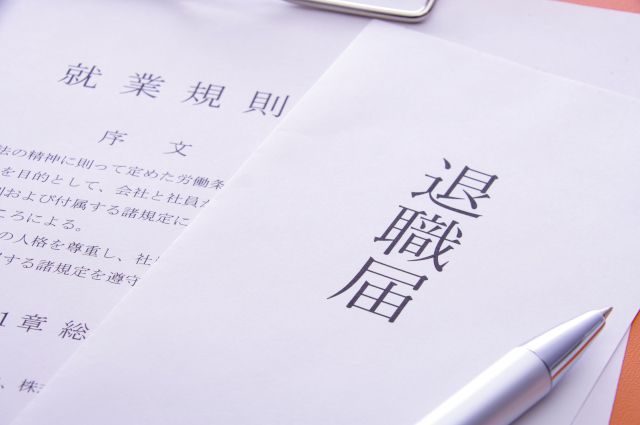
うつ病で退職する際の伝え方は、自身の状況と会社の環境に応じて適切に選択しましょう。
一般的には、直属の上司に直接伝えることが望ましいですが、うつ病の症状によっては対面でのコミュニケーションが困難な場合もあります。そのような場合は、電話やメール・退職届の郵送など、自分にとって負担の少ない方法を選ぶことが重要です。
退職の理由を説明する際は、「体調不良」や「一身上の都合」といった表現を用いて、詳細な説明を避けることも可能です。なお、会社によっては診断書の提出を求められる場合もあるため、事前に主治医に相談しておくことをおすすめします。
いつまでに伝えればいいの? 即日退職はできる?
法律上、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示は2週間前までに行うことが定められています。しかし、多くの会社では就業規則で1ヶ月前や2ヶ月前といった、より長い期間を設定していることが一般的です。そのため、まずは自社の就業規則を確認することが重要です。
なお、民法では以下のように定められています。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元
e-Gov 法令検索|民法
厚生労働省|退職の申出は2週間前までに
うつ病の場合は、この民法第628条の「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。即日退職を希望する場合は、主治医の診断書を用意し、会社に状況を説明することが重要です。
診断書があれば、会社側も従業員の健康状態を理解しやすく、即日退職に応じてくれる可能性が高まります。
どうやって伝えればいいの?
うつ病で退職する際の伝え方には、いくつかの方法があります。自身の状況や会社との関係性を考慮して、最適な方法を選択しましょう。
1. 上司に退職届を手渡す
直属の上司に退職を伝えて退職届を手渡す方法は、最も一般的で丁寧な退職の伝え方です。この方法では、上司と直接対話ができるため、自身の状況を詳しく説明したり、今後の対応について相談したりすることができます。
また、会社側の反応を直接確認できるため、スムーズな退職手続きにつながりやすいというメリットがあります。ただし、うつ病の症状が重い場合は、対面でのコミュニケーションがストレスになる可能性も考慮しましょう。
2. 電話やメール・郵送で伝える
直接伝えるのが難しい場合には、電話やメール・郵送で退職の意思を伝えましょう。この方法は、対面でのコミュニケーションが困難な場合や、即時に退職の意思を伝える必要がある場合に有効です。
電話の場合は、上司と直接話すことができるため、状況説明がしやすいというメリットがあります。メールや郵送の場合は、自分のペースで内容を整理して伝えられるため、うつ病の症状が重い場合でも比較的負担が少ないでしょう。
ただし、会社によっては書面での退職届の提出が必要な場合もあるため、事前に確認してください。
3. 退職代行を利用する
うつの症状が重くて自身で退職を伝えるのが難しい場合には、退職代行サービスを利用するのも一つの手です。退職代行サービスは、専門の業者が従業員に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な手続きを行うサービスです。この方法を利用すれば、自身で会社とやり取りする必要がなくなるため、精神的な負担を大幅に軽減することができます。
また、労働問題に詳しい専門家が対応するため、適切な退職手続きが期待できるというメリットもあります。ただし、費用がかかることや、会社との関係性が悪化する可能性があることなどのデメリットもあるため、慎重に検討しましょう。
退職届の例文を紹介
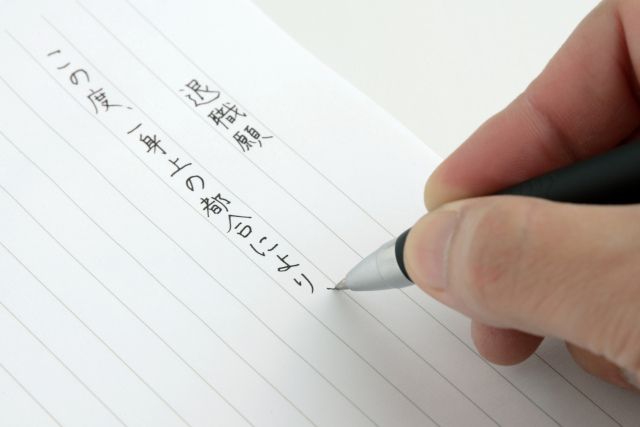
退職届を作成する際、文書やメールのどちらの形式でも、適切な例文を参考にすることで、スムーズに退職の意思を伝えることができます。ここからは、文書とメールそれぞれの退職届の例文を紹介します。
ポイントは、うつ病であっても「うつ病」という言葉を必ずしも使用しなくてもよいということです。代わりに、「体調不良」や「一身上の都合」といった表現を用いることで、プライバシーを守りつつ、退職の意思を適切に伝えることができるでしょう。
文書で伝える際の例文
退職届を文書で作成する場合、フォーマルな形式を保ちつつ、簡潔に退職の意思を伝えることが重要です。退職届の書き方に厳密な決まりはありませんが、退職日を明確に記載することで、万が一のトラブルを防ぐことができます。
また、会社独自のフォーマットがない場合は、インターネットからダウンロードした一般的なテンプレートを使用しても問題ありません。状況に応じた2つの例文を紹介します。
例文1|一身上の都合
このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
この例文は、具体的な理由を明かさずに退職の意思を伝えたい場合に適しています。必要に応じて、感謝の言葉や今後の抱負などを追加することもできます。
例文2|病気療養に専念
このたび病気治療に専念するため、令和◯年◯月◯日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。これまでのご指導に感謝申し上げます。
この例文は、健康上の理由で退職する場合に使用できます。うつ病という具体的な病名を出さずに、体調不良を理由とすることで、プライバシーを守りつつ退職の意思を伝えることができます。
メールで伝える際の例文
メールで退職の意思を伝える場合も、文書での退職届と基本的なポイントは同じです。ただし、メールの特性を考慮し、より簡潔で誠意の伝わる文章作りを心がけましょう。
特に、うつ病で既に休職中の場合は、細かい理由を説明する必要はありません。以下に、状況に応じた2つの例文を紹介します。
例文1|既に休んでいる状況
長くお休みをいただいており、申し訳ありません。体調が思うように回復せず、このまま在籍し続けるのはご迷惑をお掛けしてしまいます。〇月〇日で退職させていただきたいと思います。
この例文は、既に休職中の場合に使用できます。体調不良が続いていることを簡潔に伝え、会社への配慮も示しています。
例文2|病気療養に専念
病気療養に専念したく、〇月〇日をもちまして退職したく存じます。誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
この例文は、健康上の理由で退職する意思を伝える際に使用できます。具体的な病名を出さずに、療養の必要性を伝えています。
うつ病の方が早く退職するメリットとは?

うつ病をお持ちの方が早期に退職を決断することには、個人の健康回復と将来的なキャリア再建に大きく寄与する可能性があります。ここからは、早期退職のメリットについて見ていきましょう。
1. 治療に専念できる
うつ病をお持ちの方が早期に退職することの最大のメリットは、治療に専念できることです。職場のストレスから解放されることで、心身のバランスを取り戻すための時間と環境を確保できます。
早期に適切な治療を開始することで、症状の悪化を防ぎ、回復のプロセスを加速させる可能性も。また、治療に集中することで、うつ病の症状に苦しむ期間を短縮できる可能性も高まります。
2. 自分と向き合う時間を持てる
退職することで得られるもう一つのメリットは、自分自身と向き合う時間を持てることです。日々の業務や職場でのプレッシャーから解放されることで、ゆっくりと自己を見つめ直す機会を得ることができます。
この時間は、自分の価値観や人生の目標を再考し、今後のキャリアパスを見直すのに非常に有効です。また、心身をリセットすることで、精神的にも身体的にも回復に向かう可能性が高まります。
うつ病で退職するまでの流れを紹介
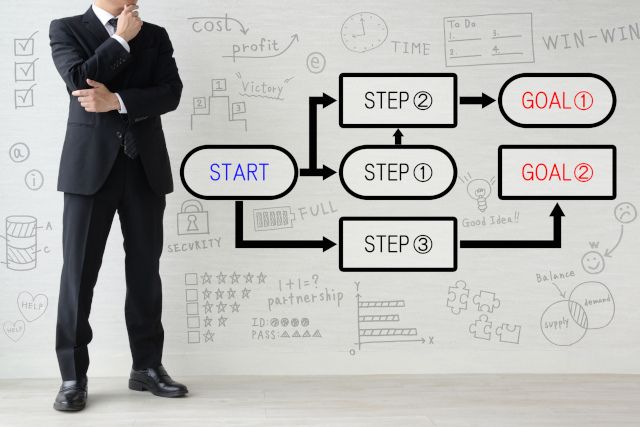
うつ病で退職を決意した場合、適切な手順を踏んで退職プロセスを進めることが重要です。これにより、スムーズな退職と、退職後の生活への円滑な移行が可能になります。うつ病で退職するまでの、一般的な流れを見ていきましょう。
1. 診断書をもらう
退職を決めたら、まず最初に行うべきことは、かかりつけ医から診断書を取得することです。診断書は、会社に対して退職の正当性を示す重要な書類となります。多くの会社では、健康上の理由による退職の場合、診断書の提出を求めています。
また、退職後に受けられる可能性のある障害年金や傷病手当金などの申請にも診断書が必要となる場合があります。そのため、早い段階で診断書を準備しておくことで、スムーズな退職手続きと退職後の支援獲得につながるでしょう。
2. 退職を伝える
診断書を取得したら、次は会社に退職の意思を伝えましょう。退職を伝える方法は、先に紹介した方法の中から、自分の状況と会社との関係性を考慮して最適なものを選択してください。
この際、診断書を提示することで、健康上の理由による退職であることを客観的に示すことができます。また、退職の時期や引き継ぎの方法などについても、可能な範囲で相談し、合意を得ておくことが望ましいです。
3. 退職の手続きを行う
退職の意思を伝え、会社側の了承を得たら、具体的な退職手続きを行います。主な手続きには、厚生年金から国民年金への切り替えや、健康保険から国民健康保険への変更などがあります。この手続きは、退職後速やかに行いましょう。
また、失業保険の手続きを行う場合は、離職票が必要となります。離職票は会社が発行するものなので、退職時に会社側へ離職票の交付を依頼しておきましょう。
退職後に受けられるサポートとは?

うつ病で退職する場合、経済的サポートを受けられるかもしれません。主なものに、傷病手当金や労災保険の休業補償給付があります。
傷病手当金は、業務外の傷病で働けなくなった場合に受給できる制度です。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の休業に対して支給されます。なお、この制度を利用する際は、医師の意見書が必要です。
一方、労災保険の休業補償給付は、業務が原因でうつ病を発症したと労災認定された場合に受けられます。
こういった制度は適用条件や申請方法が異なるため、詳細については自治体やハローワークで相談してみてください。専門家のアドバイスを受けることで、自分の状況に最適なサポートを見つけられる可能性が高まります。また、失業等給付の申請は、かかりつけ医の許可を得て再就職への活動を始めてから行うことが望ましいでしょう。
引用元
全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
全国健康保険協会|傷病手当金申請のチェックリスト
ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内
厚生労働省|労働災害が発生したとき
うつ病の方が再就職するには?

うつ病から回復した後、再就職を目指す方法はいくつかあります。ここからは、うつ病の方が回復後に再就職するための効果的な方法を見ていきましょう。
就労移行支援を活用する
就労移行支援事業所は、一般就労への移行を目指す障害者に対して支援を行う施設です。これらの事業所では、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援などを提供しています。
就労移行支援を利用すると、段階的な就労訓練や個別支援・職場開拓・就労後のフォローアップといったサポートを受けられます。
また、適性に合った職場を探す際のサポートも受けられ、就職後も継続的な支援を受けられるため、職場定着率の向上も期待できるでしょう。
リワークプログラムを活用する
リワークプログラムは、気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラムです。
リワークプログラムでは、生活リズムの改善・ストレス対処法の習得・認知行動療法・集団プログラムなどが受けられます。また、うつ病の症状改善や再発防止に効果的な認知行動療法を学び、他の参加者との交流を通じて社会性を取り戻すことができるでしょう。
引用元
一般社団法人日本うつ病リワーク協会|リワークプログラムとは
障害者向け転職エージェントを活用する
転職エージェントは、求職者の転職活動のサポートや、企業の人材採用を支援するサービスです。経験やスキル・希望に合う求人の紹介だけでなく、応募書類の添削や作成サポート・面接日程の調整・面接対策・企業とのやり取りの代行などを担ってくれます。
転職エージェントのなかには、障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化したエージェントもあります。
障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。
高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。
就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。
自分に合った方法で退職を伝えよう

うつ病で退職する際は、自分の状況に最適な方法を選んで退職の意思を伝えることが重要です。退職までの一般的な流れは、まず主治医に相談して退職のタイミングを見極めます。次に、上司や人事部門に退職の意思を伝えます。直接面談やメール・文書など、自分の状態に合わせた方法で行いましょう。
その後、退職届や診断書などの必要書類を準備して提出し、最後に引き継ぎや退職手続きを行います。
退職の伝え方は個人の状況や会社との関係性によって異なりますが、誠意を持って丁寧に伝えることが大切です。うつ病による退職は、身体的な病気と同様に正当な理由であることを忘れないでください。
退職後の再就職や新しい職場に不安を感じる方は、DIエージェントへご相談ください。DIエージェントでは、うつ病の方の再就職に関する豊富な情報提供や、ニーズに合わせた求人紹介を行っています。一人で悩みを抱え込まず、お気軽にご相談ください。
▼関連記事
うつ病の方の再就職について掘り下げています。
うつ病になったら再就職は難しい?転職活動のポイントや向いている仕事を知ろう
うつ病の方が診断後に取るべき行動や転職活動のポイントを解説しています。
うつ病でも仕事は行ける?診断後に取るべき行動や転職活動のポイントも解説

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。