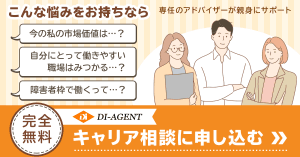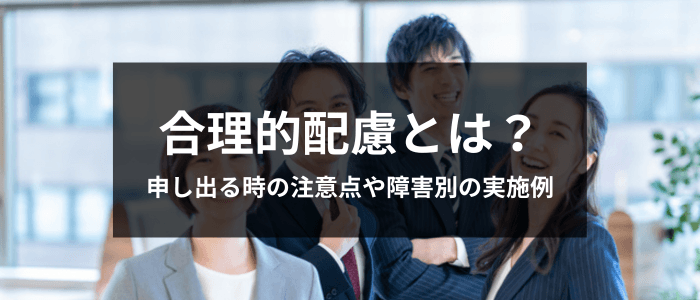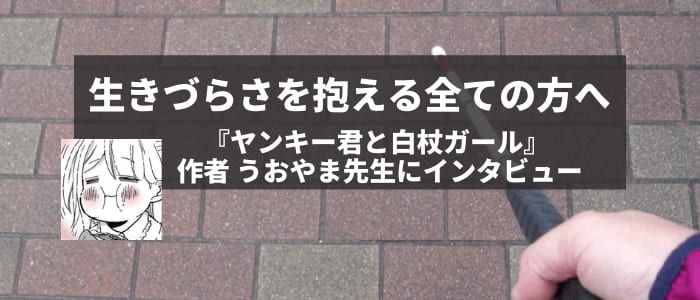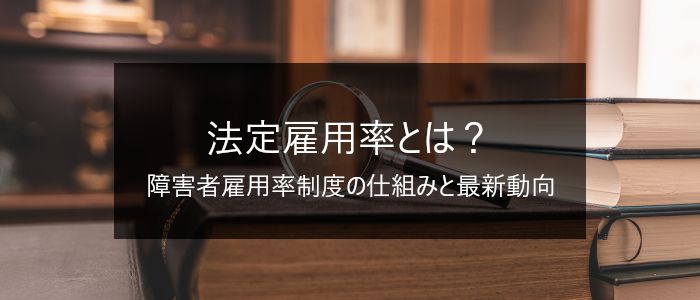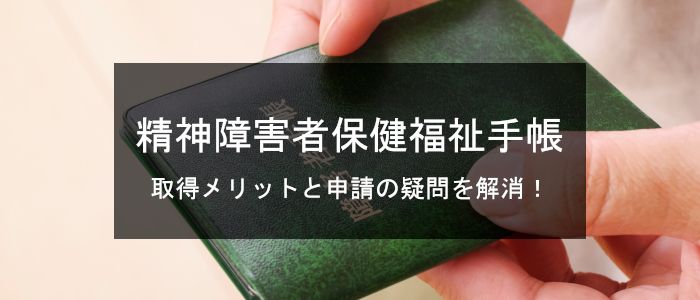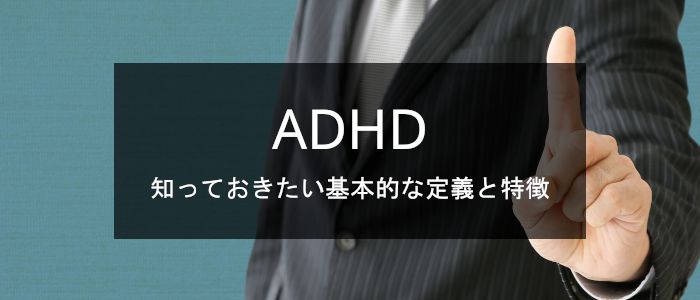「ソーシャル・スキル・トレーニング(Social Skills Training:以下、SST)」とは社会生活を送る上で必要な対人関係や自己管理能力などを養い、身に付ける訓練です。この記事では「SST」の目的や内容をわかりやすく解説していきます。
特に職場での人間関係で悩まれている方、ご自身の認知や行動を変えていきたいとお考えの成人の方は「SSTが受けられる場所」や「日常でできるSST」もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
SSTとは

「SST(エスエスティ)」とは「Social Skills Training」の頭文字をとった略称です。日本語では「生活技能訓練」や「社会生活技能訓練」ともいい、認知行動療法の一つです。
SSTとは
(一部抜粋)
SSTは1940年代の行動療法にその原型を求めることができ、その後、認知の要素を取り込みながら発展してきました。複数の理論を背景としてさまざまな技法を含んでいるところは、認知行動療法と重なるところが大きいと考えられます。SSTは効果が実証された体系的な方法で、日本でもその効果が認められ、1994年4月に精神科を標榜している保険医療機関において入院加療者を対象として「入院生活技能訓練療法」が診療報酬化されました。対人関係を中心とするソーシャルスキルのほか、服薬自己管理・症状自己管理などの疾病自己管理スキルを高める方法がスキルパッケージとして開発されています。
SSTの歴史は精神障害をお持ちの方に対しての支援がスタートですが、現在は療育の現場や復職(リワーク)や職場のストレスコントロールのためなど様々な場面でも用いられています。
引用元
生活技能訓練(Social Skills Training:SST)|障害保健福祉研究情報システム
ソーシャルスキルとは
そもそも「ソーシャルスキル」とは「社会の中で暮らしていくためのスキル」のことで、コミュニケーション(対人関係構築能力)だけでなく、生活スキル(薬を飲んで体調管理をしたり、家事やお金の管理をしたり)なども含まれています。
人は子供から大人になるにつれ、家庭や学校や様々なコミュニティで人との関わりや社会のルール(社会性)などを身に付けていきます。しかし病気や障害によってソーシャルスキルの獲得が困難または低下する場合もあるのです。
ソーシャルスキルのトレーニングとは
ソーシャルスキルはトレーニングを積むことで習得し、生活上の困難を緩和することが期待できます。
ソーシャルスキルトレーニングの特徴として、ロールプレイをおこなったりグループワークをしたりと実践形式の訓練メニューが用意されていることが多いです。
「発達障害専門プログラム ワークブックⅠ」によれば、SSTでは以下の6つの基本スキルが重要と言われています。
- 視線を合わせる
- 手を使って表現する
- 身を乗り出して話す
- 明るい表情
- はっきりと大きな声
- 適切な内容
引用元
「発達障害専門プログラム ワークブックⅠ」12p|昭和大学発達障害医療研究所(2015)
発達障害・精神障害との関連
SSTは発達障害をお持ちの方や精神障害をお持ちの方に対しておこなわれています。
ストレスへの適切な対処など統合失調症、うつ病をお持ちの方へは治療的観点からSSTが用いられる場合もあります。
自閉症スペクトラム(ASD)
- 自分の気持ちを伝える、相手の気持ちを読み取ることが苦手
注意欠如・多動症(ADHD)
- 一方的にしゃべりすぎる
- 意欲が減退し、定常的な服薬が難しくなる
精神障害(統合失調症やうつなど気分障害)
- 必要以上に自分を責めてしまう、物事をネガティブに捉えてしまう
上記のような場合、SSTが効果的に働く可能性があります。
引用元
こころの病気を知る-発達障害|厚生労働省
こころの病気を知る-うつ病|厚生労働省
自閉症スペクトラムの人々の就労に向けたSST|米田衆介
SSTのメリット

SSTを実践するメリットは、社会生活を営む上での困りごとの解決に役立ち、QOLの向上につながることです。また精神疾患を悪化させないためや二次障害を引き起こさないために活用するのも有効でしょう。
SSTが役立つ場面の例
- 職場の人間関係を円滑にする
- きちんと薬を服用することができ、健康な状態を維持する
- 「嫌だな」と感じる場面できちんと断ることができる……など
基本をおさえ応用がきくように様々なケーススタディをおこないますので、自分なりの対処法を見つけていける力が身に付きます。
SSTの具体的な内容

SSTは具体的にどのような内容をおこなうのでしょうか。ここでは一例として「ロールプレイ」「ディスカッション、ディベート」「共同行動」「ゲーム」「ワークシート・絵カード・ソーシャルストーリー」を紹介していきます。
ロールプレイ
SSTの代表的な内容の一つとして「ロールプレイ(役割演技)」が挙げられます。
まずは「ある場面」に対して、どのように振舞うのが適切なのかをまずは考え、お題となるシチュエーションで指導担当者や参加者同士で実際に演技をします。演じた後は、「相手を気遣った言葉かけができていましたね」「こういった言い方もありそうですね」などといったフィードバックが得られます。
その人にとって、課題となっている・課題となりそうな言動や場面をアレンジしつつおこなっていきます。
ディスカッション、ディベート
ディスカッション、ディベートは相手を言い負かすことではありません。
SSTにおいては、言葉のキャッチボールの訓練をおこないます。相手の意見を聞きつつ、自分の意見を述べる練習をしていきます。
共同行動
特に療育の現場や成人もデイケアにおいて、工作、調理などの共同行動をおこなうことがあります。活動を通して他の人との相談、役割分担、助けあいなどが身に付くでしょう。
ゲーム、レクリエーション
「SSTなのにゲーム?」と不思議に思われる方もいるかもしれません。
ゲームは「ルールを守る」「勝ち負けを受け止める」「相談・協力」といったスキルが楽しく身に付きます。一見気晴らしのように感じる就労移行支援事業所でのレクリエーションも実はSSTの要素が含まれていることもあるのです。
ワークシート・絵カード・ソーシャルストーリー
書き込み式のワークシート、図式化された絵カード、ソーシャルストーリーなどをSSTに用いることもあります。
課題になっている言動を文章や図で表現することで、意識化をします。
ソーシャルストーリーとは
ソーシャルストーリーとは「叙述文」(事実)・「視点文」(心の動き)「指示文」(望ましい振る舞い)などから成り立つ短いストーリーです。課題となる状況を文章として、書き出したり、それを声に出して読んだりします。
たとえば、「上司に質問したいことがあった時、周りの状況を見ずに突発的に聞いてしまい、怒られてしまう」という悩みがあったとします。
例)
「初めて取り組む仕事が発生した」
「やり方が分からないので、上司にやり方を聞く必要がある」
「しかし、上司は他の人と話している」
「私は気になっているので今すぐ聞きたい」
「二人は真剣に話しているので、急に私が話しかけたら上司も話し相手も驚くかもしれない」
「我慢して、二人が話し終わってから上司に話しかける」
「上司も落ち着いて私の話を聞いてくれる」
このように書くことで、「こんな時どうしたら良いか」に気づくことができるでしょう。
引用元
自閉症スペクトラム障害児に対するソーシャル・ストーリーの効果:事例研究の展望|藤野 博(2005) 東京学芸大学紀要.第1部門,教育科学,56:349-358
通常の学級における特別な教育的ニーズのある子どもへの支援|千葉県総合教育センター
日常で取り入れられるSST

SSTは必ずしも専門知識をもった指導者のもと、特別な施設にておこなわれるだけではありません。日常でも意識して取り入れることができますので、以下を参考に心がけてみてください。
挨拶をする
挨拶は人とのコミュニケーションの第一歩です。適切なタイミングで適切な言葉を発することができるようになるために、人によっては練習が必要かもしれません。意識的に挨拶をしてみましょう。
いきなり「雑談を上手に続けられるように目指す」と高い目標を掲げるよりも、「挨拶をしっかりする」と心がけるだけで周囲からの印象は驚くほどアップしますよ。
相手の気持ちを察する
次に、相手が考えていることを意識的に想像する訓練を日常的におこなってみましょう。自然と相手の気持ちを理解できるようになっていきます。
療育(対:子供)の場面では人形を用いて「登場キャラクターの気持ちを考える」といったトレーニング方法もあります。
会話をする
特に感情のコントロールが難しい方や発達障害の方は、相手を傷つける言葉を言ってしまったり、相手にとって興味のない話を続けてしまうこともあります。
会話・対話とはあらゆるコミュニケーションスキルの総合格闘技のようなものです。相手の話を聞き、意図をとらえ、適切な答えを返す必要があります。
まずはスモールステップで、「一問一答から始めてみる」「台本を用意して会話の練習をしてみる」「フリートークをして、お互いにどう思ったかを振り返る」などから始めてみてはいかがでしょうか?
SSTを実践する際のポイント

SSTを効果的に実施するためには、参加者がリラックスして活動に取り組めるような工夫や配慮が大切です。進行役は、雰囲気作りや参加者が自己表現しやすい環境を整える必要があります。さらに、日常生活に役立つ具体的なスキルを磨けるような練習を取り入れることも重要です。
ここからは、SSTを実践する際のコツやポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1. 楽しい雰囲気の演出とアイスブレイクの活用
SSTを効果的に行うためには、参加者が楽しめる雰囲気作りが欠かせません。
緊張をほぐし、リラックスした状態で活動に臨めるようにすることが、良い結果を生むポイントとなります。アイスブレイクなどの活動を取り入れることも、この目的を達成するための手段の一つです。
このような雰囲気作りは、参加者が自信を持って活動に参加し、効果的にスキルを学べる環境を提供するために不可欠です。緊張が解け、リラックスした状態で活動に臨むことで、参加者はより積極的に参加し、トレーニングの内容を深く理解することができるでしょう。
アイスブレイクとは?
アイスブレイクは、参加者同士が互いに知り合い、信頼関係を築くための活動です。会話や簡単なゲームを通じて、最初の緊張感を和らげ、参加者の関心を引き付けます。
アイスブレイクを通じて、初対面の参加者がリラックスできるようにするだけでなく、グループの一体感を作り出します。楽しい雰囲気を作ることで、その後の活動に積極的に参加しやすくなります。
3. フィードバックの重要性
SSTにおいて、フィードバックは参加者が自分の強みや改善点を認識するために非常に重要な要素です。効果的なフィードバックを行うことで、参加者は自分のコミュニケーションスキルがどう進歩しているかを理解し、次回の活動に対する意欲が高まるでしょう。
特に、「良かった点」や「できている点」など、ポジティブなフィードバックを重視することが大切です。ポジティブなフィードバックは次回以降の参加のモチベーションが高まるだけでなく、スキルの定着しやすさにも影響があります。
4. 反復練習と日常生活への汎化
SSTで学んだスキルを日常生活に活かせるようにするためには、実際の生活に即した反復練習が必要です。定期的に練習を重ねることで、習得したスキルが定着し、無意識のうちに使えるようになるでしょう。
特に、日常的なシチュエーションでそのスキルを活用することが、実践的な力を高める鍵となります。例えば、家庭や職場でコミュニケーションスキルを実際に試し、状況に応じた適切な反応を取る練習をすることが、スキルの向上につながります。
5.コミュニケーションのスキルを具体的に身につける
SSTでは、単に一般的なコミュニケーション能力を高めるだけでなく、具体的なスキルを身につけることが重要です。例えば、相手の気持ちや状況を確認する声かけや、相手の状況に配慮する言葉を使うことが挙げられます。
また、感謝していることをきちんと伝えることも、良好な関係を築くために有効なコミュニケーション技術です。こういった具体的なスキルを身につけることで、よりスムーズで効果的なコミュニケーションが可能になるでしょう。
具体的なコミュニケーションのスキル
具体的なコミュニケーションのスキルには、以下のようなものがあります。
- 今、話しかけても大丈夫ですか? - 相手の都合を確認する
- お忙しいとは思うのですが - 相手の状況を尊重する
- クッション言葉を使う - 相手が気持ちよく受け入れてくれるための言葉
- 感謝を伝える - 頼みごとを受け入れてくれたことへの感謝を伝える
これらのスキルを具体的に身につけることで、日常生活でのコミュニケーションがスムーズに行えるようになります。
6. 対象者に合わせたアプローチと柔軟性
SSTでは、参加者一人ひとりの個性や特性に応じた柔軟なアプローチが求められます。参加者の中には、人前で話すことが苦手な方もいるかもしれません。そういった参加者はグループ活動ではなく、一対一のセッションを行うことが適切です。
また、ロールプレイやゲームに参加することに苦手意識を感じる場合は、観察者になるというのも有効です。観察も参加の方法の一つで、無理なく学びを深めることができるでしょう。
重要なのは、それぞれのペースに合わせて、参加しやすい環境を作ることです。
SSTはどこで受けられる?

ここまで読んで「SSTを受けたい」と思われた方へ、大人がSSTを受けられる場所・機会を紹介していきます。
受講条件がある場合や値段も様々なので、希望する場合は実施先に問い合わせてみましょう。
SSTが受けられる最も身近な場所は「病院やクリニック」です。精神科・心療内科が実施しています。
このような場所では、精神科看護師や作業療法士・臨床心理士などがSSTを学んで習得したうえで、プログラムを組んでいることが多いです。服薬や体調管理も含めたSSTが必要な方はまずはかかりつけ医にSSTを実施していないか確認しましょう。
他にも「自立訓練(生活訓練)事業所」といった福祉事業所や大学などの研究機関でもSSTが実施されていることがあります。
しかし、SSTは必ずしも精神科を受診している方だけが対象ではありません。特に「働く」に特化したSSTが受けられる場所も存在します。
働くことに障害がある方に向けたSST
働く上で困難を感じている方は、目的に応じてSSTが受けられます。
リワークSST
「リワーク」つまり「復職」のためのSSTです。
こちらも病院(精神科等)にくわえ、EAPの運営企業などで実施されていることがあります。
十分な休養が取れた後は、規則正しい生活リズムを取り戻し体力の回復を目指したり、ストレス対応能力を伸ばすようなプログラムが用意されています。
一般企業における定着支援のためのSST
稀ではありますが、障害者雇用をおこなう企業が独自で定着支援サポートを担っている場合もあります。このようなサポート体制があるのは安心ですね。
ジョブコーチを導入している企業では、ジョブコーチとの時間にSSTを実施することもあります。
引用元
企業における障害者の定着支援とSST|大東コーポレートサービス株式会社
就職、転職準備のためのSST
「働くことに不安がある」「人間関係でつまづいてしまって仕事を転々としている」という方は働くための準備をしましょう。以下の場所はSSTを実施しています。
就職・転職に役立つSSTが受けられる場所
- 若者サポートステーション(通称:サポステ)
- 障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつ、就ぽつ)
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援A型・B型事業所
また上記以外にも不定期で「SST」のイベントが開催されていることもありますので、探してみましょう。
引用元
「うつに対するSST(リワークプログラム)|実践:ワークショップから学ぶSST 第8巻」|中島映像教材出版
就労移行支援事業所「ワークイズ」でおこなうSSTの例

施設管理責任者の大浦さん
就労移行支援事業所「ワークイズ」(東京都・大田区)では社会の場で必要な内容を座学形式で教えています。より具体的には「上手な話の聞き方」、「あたたかい言葉がけ」などを一緒に考えていきます。
決まりきったプログラムやテキストをこなすのではなく一人ひとりが困っていること、達成したいことを元にプログラムを組んでいます。
子供がSSTを受けられる「テラコヤキッズ」

前項で紹介したSSTは、主に大人・社会人向けのものです。ここからは、子供がSSTを受けられる「テラコヤキッズ」について紹介します。
テラコヤキッズとは
テラコヤキッズは、子供の将来を見据えた療育を行う放課後等デイサービスです。一人一人の個性や特性に合った療育を行い、家庭、学校、医療、地域社会とのネットワークも重視しながら子供の自立を目指します。
ここでは、子供が社会生活や人間関係スキルを学ぶための支援が提供されています。その中でも特に、子供の発達に必要な基本的なスキルや社会参加スキルを養うためのプログラムが充実しています。
テラコヤキッズでは、子供一人一人に合わせたカスタマイズされた支援を提供し、子供のニーズに応じた療育が行われます。
教室は東京・神奈川・大阪
テラコヤキッズの教室は以下の場所にあります。
- 新宿本教室: 東京都新宿区住吉町2-10 ソフィアMビル3階。都営新宿線曙橋駅より徒歩1分、東京メトロ丸の内線四谷三丁目駅より徒歩6分。
- ゆめ気球教室: 東京都大田区蒲田1丁目25-7 グレードワン・ヒラタ 1F。JR 蒲田駅東口より徒歩5分。
- 川崎教室: 神奈川県川崎市川崎区中島2-1-3 クレストHY102。JR川崎駅東口より徒歩20分、市バス「市立川崎高校前」より徒歩1分。
- 阿倍野教室: 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-11-22 阿倍野カルチェ美章園101号室。JR阪和線美章園駅より徒歩4分。
各教室は、利便性とアクセスの良さを考慮して設置されています。
親子で参加できるイベントやワークショップも
テラコヤキッズでは、親子関係を強化するために、親子で参加できるイベントやワークショップを定期的に開催しています。これは親子間のコミュニケーションを深めることを目的としており、子供と親が一緒に参加することで、より強い絆を築くことができるでしょう。
また、親同士のネットワークを促進し、情報交換や相談の場の提供も行っています。子供本人はもちろん、親子や家族全体のサポートシステムもあり、子供の成長を支える環境が整えられています。
さらに、親同士の交流を通じて、子供の教育やケアに関する情報やアドバイスを共有することも可能です。親たちの負担を軽減し、子供の育て方に自信を持って取り組むことができるようサポートしています。
「生きにくさ」の解消につながる可能性大!SSTを受けることを検討してみましょう

大人でもソーシャルスキルを身に付けるのに手遅れということはありません。専門家や同じような悩みを抱えているメンバーから、フィードバックを受けることで、より自分らしく生きるためのヒントが見つかるかもしれません。
「人間関係や生活がどうしてもうまくいかない、でもどうしたらいいか分からない」といった方はSSTを受けることを検討してみてはいかがでしょうか?
SSTは大人だけでなく、子供にも効果的で、成長の過程で大切なスキルを身につけるために活用できます。
特に、子供の頃に適切なソーシャルスキルを学ぶことは、学校生活や将来の人間関係において大きな差を生むことがあります。子供が自分の気持ちをうまく伝えたり、他者と円滑にコミュニケーションを取る力を養うためには、早い段階でのSSTが非常に有効です。
SSTで身に付けたスキルは就職活動・転職活動でも必ず活きてきますよ!

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。