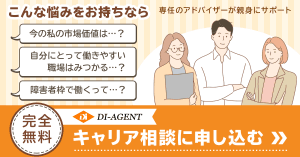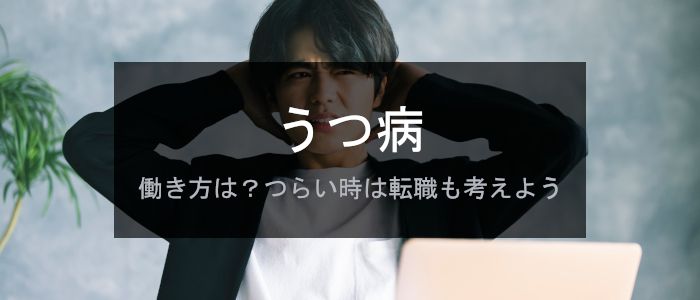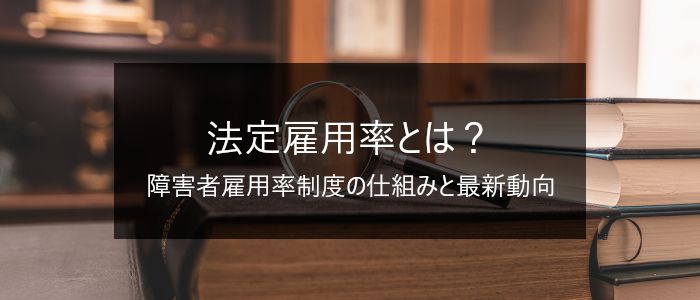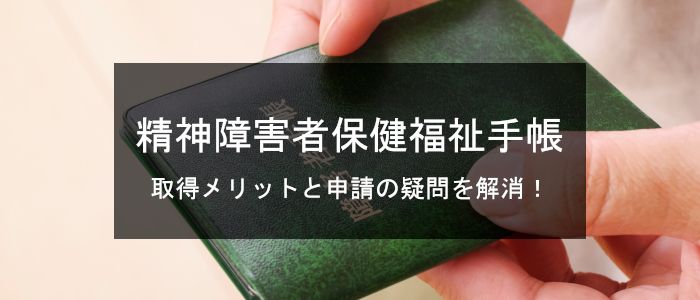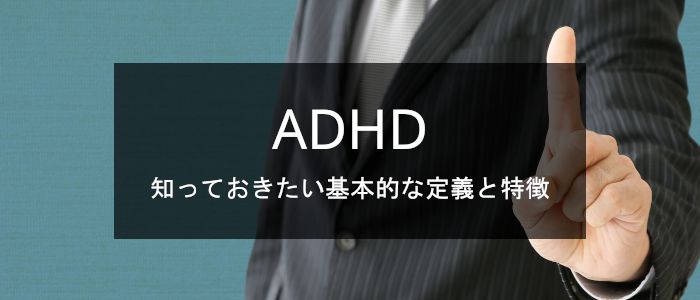躁うつ病(双極性障害)を抱えながら、自分らしく輝けるキャリアを築きたいと願う方は少なくありません。しかし、気分の波が激しい双極性障害を持つ方が仕事をする際、集中力の維持・人間関係の構築・体調管理など、さまざまな困難に直面することも事実です。
そこで今回は、双極性障害をお持ちの方が仕事で抱えやすい具体的な悩みから、症状への理解が得られ、安心して働ける職場環境の選び方までを解説します。また、就労移行支援事業所をはじめとする、双極性障害の方をサポートする就労支援機関の情報も紹介します。
「双極性障害だから」とキャリアを諦める必要はありません。障害者雇用に関する知識を身につけ、自分に合った働き方を見つけるための第一歩を踏み出しましょう。
双極性障害(躁うつ病)とは?

双極性障害は、以前は躁うつ病として知られていた精神疾患であり、気分の極端な変動が特徴です。具体的には、気分が高揚し活動的になる「躁状態」と、気分が著しく落ち込み意欲が低下する「うつ状態」が繰り返されます。
これらの状態は、単なる気分の浮き沈みとは異なり、日常生活や社会生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。双極性障害の症状や経過は人それぞれであり、躁状態とうつ状態の現れ方や期間・頻度も異なります。しかし、適切な治療とサポートによって、症状をコントロールし、安定した生活を送ることが可能です。
以下で、双極性障害の種類や、うつ病との違いについて詳しく見ていきましょう。
引用元
国立国際医療研究センター病院|双極性障害とは?
こころの情報サイト|双極性障害(躁うつ病)
双極性障害の種類とは?
双極性障害は、症状の現れ方によって大きく二つの型に分けられます。躁状態の程度・うつ状態の有無・症状が日常生活に与える影響によって区別されます。
双極I型障害と双極II型障害は、それぞれ異なる特徴を持ち、治療のアプローチも異なる場合も。双極I型障害と双極II型障害について、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
双極性障害Ⅰ型
双極性障害I型は、顕著な躁状態を特徴とする精神疾患です。この躁状態は、単なる気分の高揚を超え、社会生活に深刻な支障をきたすほど激しい場合があります。
例えば、ほとんど眠らずに活動し続けたり、普段よりも多弁になったり、考えが次々と湧き上がって止まらなくなったりすることなどが挙げられます。
また、誇大妄想を抱いたり、危険な行動に走ったりすることも。衝動的な買い物や投資で財産を失ったり、見知らぬ人に過剰に話しかけたり、怒りっぽくなったりすることもあるようです。
こういった症状は、本人だけでなく、周囲の人々にも大きな負担をかけることがあります。
双極性障害Ⅱ型
双極性障害II型は、I型に比べて躁状態の程度が軽い「軽躁状態」が特徴です。
軽躁状態は、気分が高揚し、活動的になるという点では躁状態と共通していますが、社会生活に著しい支障をきたすほどではありません。むしろ、普段よりも創造性が高まったり、集中力が増したりすることもあるようです。
しかし、軽躁状態は、本人にとっては調子がよいと感じることもあるため、病気であるという認識を持ちにくいこともあります。周囲の人が普段と違う様子に気づき、専門家の診察を勧めることが重要です。
うつ病とはどこが違うの?
うつ病も精神疾患の一つであり、持続的な気分の落ち込みや、興味や喜びの喪失が主な症状です。一日中気分が沈んでいたり、何をするにも楽しめなかったりといった精神的な症状に加え、不眠や食欲不振・強い疲労感といった、身体的な症状が現れることもあります。
こういった症状は日常生活に大きな支障をきたし、仕事や学業・人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。うつ病は、適切な治療を受けることで改善が期待できる病気ですが、放置すると症状が悪化し、社会生活を送ることが困難になってしまうかもしれません。
双極性障害のうつ状態とは?
双極性障害のうつ状態は、うつ病と同様に、気分の落ち込みや意欲の低下といった症状を伴います。しかし、双極性障害のうつ状態は、うつ病とは異なる特徴があります。それはうつ病の治療薬である抗うつ薬が効きにくい場合があるということです。
それどころか、抗うつ薬が躁状態を引き起こしてしまうリスクも。そのため、双極性障害のうつ状態の治療には、気分安定薬と呼ばれる薬が用いられることが一般的です。
双極性障害の方が仕事で抱えやすい悩みとは?

双極性障害をお持ちの方は、職場において困難に直面することは少なくありません。気分の波が激しいことから、集中力の維持や人間関係の構築・安定したパフォーマンスの発揮などが難しくなることがあります。
こういった悩みは、仕事の成果だけでなく、精神的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。ここからは、双極性障害の方が仕事で抱えやすい具体的な悩みについて見ていきましょう。
1. ミスが増えてしまう
双極性障害をお持ちの方は、仕事におけるミスが増えてしまったと感じることがあるかもしれません。これは、双極性障害の症状として認知機能の低下が見られる場合があるのが原因と考えられます。
認知機能とは、記憶力・注意力・集中力・判断力など、情報を処理し、活用するために必要な能力のことです。
国際双極症学会で公開されている「住吉太幹, 長谷川由美, 末吉一貴:双極性障害における認知機能 -当事者のための小冊子; 国際双極性障害学会編, 2020」には、以下のように記載されています。
最近の研究では、一般に30~40%の双極性障害患者は、年齢、学歴から期待されるレベルの認知機能検査の成績を示します。また、注意のような限られた認知機能領域に問題を持つ患者が、同じくらいの割合で見られます。残りの患者には、注意、記憶、明確に思考する能力のような複数の認知機能領域に障害があります。以上をまとめると、認知機能がどのように、どの程度障害を受けるかは、人により違いがあります。
引用元
住吉太幹, 長谷川由美, 末吉一貴:双極性障害における認知機能 -当事者のための小冊子; 国際双極性障害学会編, 2020|双極性障害における認知機能
また、「寛解期日本人双極性障害患者の認知機能解析」では、以下のように記載されています。
認知ドメインごとの比較では、視覚学習、社会認知、処理速度、およびMCCB総合スコアにおいて、患者群で優位にその得点が低かった。メタ解析では、双極性障害患者は、全ての認知ドメインおよびMCCB総合スコアにおいて、優位な認知機能低下が認められた。
引用元
公益社団法人 日本精神神経学会|寛解期日本人双極性障害患者の認知機能解析
このことから、双極性障害による認知機能の低下が、ミスの増加につながっていると推測できます。
2. 人間関係でのトラブルが増える
躁状態の症状の一つとして、ちょっとしたことで怒りやすくなったり、感情的になりやすくなったりすることがあります。この症状は、職場での人間関係に悪影響を及ぼす可能性も。
例えば、同僚の言動に過剰に反応してしまって口論になったり、感情的なメールを送ってしまったりするかもしれません。また、躁状態では、自信過剰になり、周囲の意見を聞き入れなくなることもあるため、チームワークを損なう可能性もあります。
3. 無断欠勤・遅刻をしてしまう
うつ状態になると、気分が沈み込み、意欲が低下するため、仕事に行くことが困難になることがあります。朝起き上がることができず、無断欠勤や遅刻をしてしまうことも。
また、うつ状態では集中力や判断力も低下するため、仕事の効率が著しく低下し、職場での評価が下がることもあります。さらに、このことが原因でますます落ち込んでしまう、悪循環に陥ってしまう可能性も高いです。
4. 身体的症状で体調不良に
双極性障害に伴う気分の変動は、身体的な症状を引き起こすことがあります。例えば、食欲不振や過食・不眠や過眠・頭痛・倦怠感などです。
こういった体調不良が起きてしまうと、仕事に集中することが困難になります。また、体調不良が続くと、精神的な負担も増し、さらに症状が悪化する可能性も考えられるでしょう。
5. 仕事を抱えすぎる
躁状態の時には、普段よりも意欲が高まり、自信に満ち溢れることがあります。その結果、自分一人では抱えきれない量の仕事を引き受けてしまうかもしれません。
しかし、その後うつ状態に転じると、引き受けた仕事を達成することができなくなり、周囲の信用を失ってしまいます。また、抱え込んだ仕事のプレッシャーが、うつ状態をさらに悪化させてしまうこともあります。
双極性障害の方に向いている仕事・職場とは?

双極性障害をお持ちの方にとって、適切な仕事や職場環境を見つけることは、安定した生活を送るための重要な要素です。症状の波や特性に配慮した環境で働くことで、職場でのストレスを軽減し、長期的に就労を継続することが可能になるでしょう。
ここからは、双極性障害をお持ちの方に特に向いている仕事や職場の特徴について見ていきましょう。
1. 症状への理解が得られる
双極性障害の治療には、定期的な通院や服薬が欠かせません。そのため、これらの必要性について、理解や配慮が得られる職場環境が重要です。
例えば、通院のための休暇を取りやすい雰囲気や、服薬のタイミングに合わせて休憩を取れるような柔軟な勤務体制がある職場が理想的です。
また、双極性障害のお持ちの方にとっては、在宅ワークもおすすめ。在宅ワークであれば、通勤によるストレスを避けられるだけでなく、自分のペースで休憩を取りながら仕事を進められるため、症状管理がしやすくなります。
2. 業務量や勤務時間に変化が少ない
双極性障害の方にとって、安定した生活リズムを維持することは非常に重要です。そのため、年間を通して業務量や勤務時間に大きな変動がない仕事や職場が適しています。
例えば、定型的な事務作業や、一定のペースで進行するプロジェクト型の仕事などが挙げられます。反対に、時期によって繁忙期が存在し、業務量が一気に増加するような職場は避けた方がよいでしょう。
急激な業務量の増加は、生活リズムを崩す原因となり、症状の悪化につながる可能性があります。
3. コミュニケーションが少ない
人との交流が比較的少なく、多くの人とコミュニケーションを取る必要がない仕事や職場環境も、双極性障害をお持ちの方に適しています。これは、人間関係でのトラブルを起こしにくく、ストレスを軽減できるためです。
例えば、データ入力やプログラミング・ライティングなどの仕事は、他者とのコミュニケーションが少なく、自分のペースで作業を進められるため、おすすめです。ただし、完全に孤立した環境は避け、必要最小限のコミュニケーションは維持しましょう。
4. 障害者雇用に積極的
障害者雇用に積極的な職場は、双極性障害をお持ちの方にとって、働きやすい環境と言えます。このような職場では、症状が出た際にも適切な配慮を受けやすく、必要な支援を得られる可能性が高いからです。
例えば、業務内容の調整や勤務時間の柔軟な変更など、一人ひとりの状況に応じた対応が期待できます。障害者枠での就職は、法定雇用率の観点から企業側にもメリットがあるため、より安定した雇用を得られる可能性が高くなります。
双極性障害の方におすすめの就労支援機関を紹介
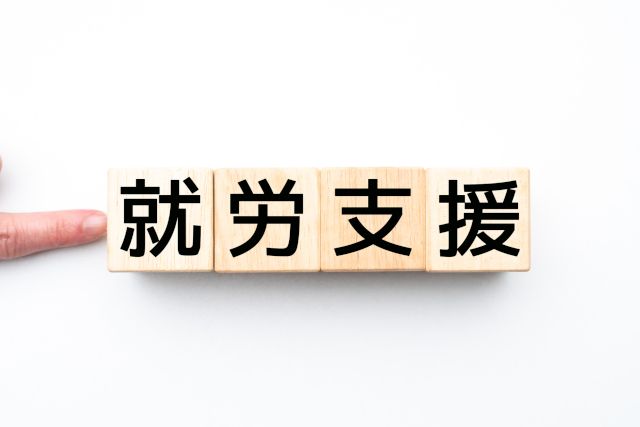
双極性障害をお持ちの方が就労を目指す際、支援機関を活用することで、より円滑に就職活動を進めることができます。こういった機関は、適切なサポートを提供し、就職後の職場定着までをフォローしてくれます。
ここからは、双極性障害をお持ちの方におすすめの就労支援機関について見ていきましょう。
1. 就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般就労への移行を目指す障害者の方を支援する施設です。この事業所では、事業所内や企業における作業や実習を通じて、就労に必要なスキルを身につけることができます。
また、適性に合った職場探しや、就労後の職場定着のための支援も行っています。具体的には、履歴書の書き方や面接対策やビジネスマナーの習得など、就職活動に必要な準備のサポートです。
さらに、企業実習の機会を提供することで、実際の職場環境を体験し、自分に合った仕事を見つけられる手助けになります。
2. 地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害者職業カウンセラーなどの専門スタッフを配置し、ハローワークや障害者就業・生活支援センターと密接に連携しながら、障害のある方の就職や職場定着、職場復帰を支援する機関です。
この期間では就職を目指す障害者の方だけでなく、障害者雇用を検討している、あるいは雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対しても、支援やサービスを提供しています。
例えば、職業評価や職業準備支援・ジョブコーチによる支援など、個々のニーズに応じた専門的なサービスを受けることができます。
引用元
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|地域障害者職業センター
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|東京障害者職業センターについて
3. 精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて各都道府県に設置が義務付けられている機関です。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、以下のように定められています。
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
引用元
e-Gov 法令検索|精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
この機関では、心の問題や精神疾患で困っている本人だけでなく、そのご家族や関係者の方からも相談を受け付けています。
双極性障害を含む精神疾患に関する専門的な知識を持つスタッフが、医療や福祉サービスの利用に関する情報提供や助言を行っています。また、就労に関する相談も受け付けており、必要に応じて適切な支援機関や医療機関を紹介してくれるでしょう。
引用元
東京都福祉局|東京都立精神保健福祉センター
東京都福祉局|東京都立精神保健福祉センターとは
4. 障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、全国に設置されている支援機関です。この機関では、雇用・保健・福祉・教育など、各関係機関と連携しながら、障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な支援を行っています。
主な支援内容は、就職に向けた準備支援・職場定着に向けた支援・日常生活や地域生活に関する助言などです。特に、就労と生活の両面からサポートを受けられる点が大きな特徴です。双極性障害をお持ちの方が症状管理と就労の両立を図る際、非常に有効な支援を受けることができるでしょう。
引用元
厚生労働省|障害者就業・生活支援センターについて
厚生労働省|障害者就業・生活支援センターの概要
症状への理解が得られる仕事・職場を探そう

双極性障害をお持ちの方が、仕事で直面しやすい課題は多岐にわたります。集中力の低下によるミスの増加や気分の変動による人間関係のトラブル・うつ状態による無断欠勤や遅刻・身体的な不調・そして躁状態の時に仕事を抱えすぎてしまうことなどです。
こういった課題に対応し、長期的な就労を実現するためには、何よりも症状に対する周囲の理解が得られる職場環境を見つけることが大切です。
双極性障害の方にとって、働きやすい職場にはいくつかの特徴があります。まず、治療のための通院や服薬に対する理解と配慮があることが重要です。また、業務量や勤務時間の変動が少なく、生活リズムを崩しにくい環境も望ましいでしょう。
さらに、他者とのコミュニケーションが比較的少ない仕事や、障害者雇用に積極的な企業を選ぶことも有効です。在宅ワークも、通勤の負担を軽減し、自分のペースで仕事を進められるため、症状管理がしやすい働き方と言えます。
就労に関する支援が必要な場合は、各支援機関を利用してみてください。就職に関する相談や職業訓練、職場定着支援など、様々なサポートを受けることができます。
「双極性障害があってもキャリアを諦めたくない」「自分に合った職場で、能力を最大限に発揮したい」という方は、ぜひDIエージェントにご相談ください。DIエージェントでは、専門のキャリアアドバイザーが状況や希望を丁寧にヒアリングし、最適なキャリアプランを提案いたします。
個性と能力が活かせる職場を見つけ、充実したキャリアを築けるようサポートを行っています。まずは、無料の会員登録をしてみてはいかがでしょうか。
▼関連記事
双極性障害の方が就職・転職活動を成功させるポイントを解説しています。
双極性障害の方が就職・転職活動を成功させるポイントや適した働き方を解説
双極性障害の方に適した職場環境について掘り下げています。
双極性障害だと仕事が続かない?転職を繰り返すことなく長く勤められる職場環境とは

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。