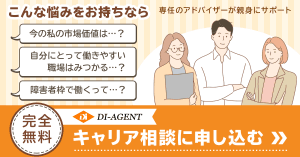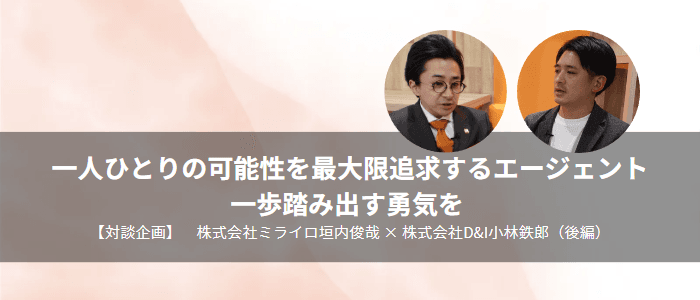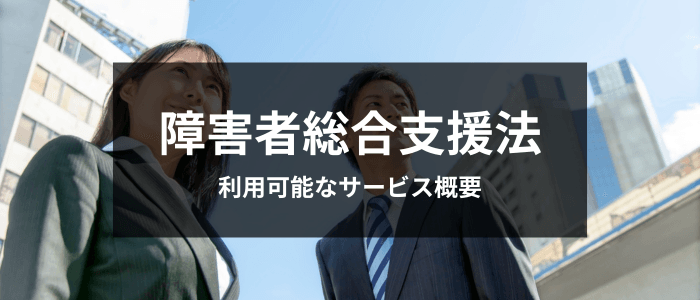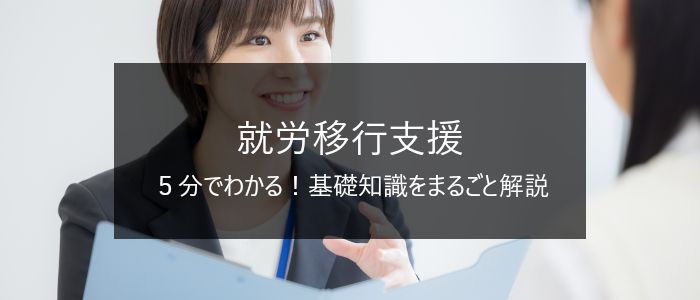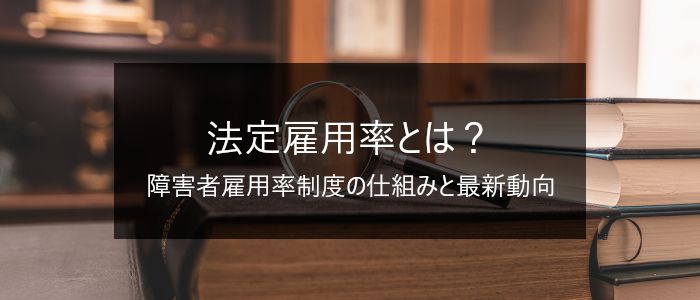身体障害という言葉はよく聞かれますが、障害にはさまざまな種類があり、症状も多岐にわたります。そこで、身体障害の定義や種類について理解を深めましょう。
また、身体障害者が働く場合の就労形態にも3つのパターンがあるので、どんな働き方なのかを解説します。そのほか、主に経済面で身体障害者の方が受けられるサービスを紹介するので、使えるサービスはぜひ活用しましょう。
身体障害を抱えていても、より生活しやすくなる方法はたくさんあるため、ぜひ最後まで読んで今後に役立てていただければ幸いです。
身体障害とは?概要や身体障害者の定義

身体障害とは、生まれつき(先天性)、または病気・事故・怪我によって(後天性)、視覚・聴覚や手足といった身体の機能に障害を抱えている状態のことです。詳しい種類と内容は、次の章で解説するのでそちらをご覧ください。
また、身体障害者とは、身体障害者福祉法第四条で
『「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。』
と定義づけられています。
「別表」とは、身体障害者福祉法の「別表第五号」のことです。表内に詳しい障害の内容や等級が記されています。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体障害を持つ方に対して都道府県知事や市長が交付する手帳のこと。ただし、交付を受けるためには所定の申請が必要です。
身体障害者手帳には、写真や氏名などの個人情報のほか、障害の種類や等級などが載っており、手帳を持っていることでさまざまな支援やサービス(内容は後述)を受けられます。
詳細は下記ページでご確認ください。
身体障害の5つの種類と症状

身体障害は、大きく分けると下記の5種類に分類されます。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能の障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓)
障害ごとに等級も定められています。1級が最も重度で、大きく欠損している・生活での動作が不可能などの状態です。
そこで、それぞれの障害の症状や等級を下記で項目ごとに解説します。
引用元
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)|厚生労働省
1.視覚障害
視覚障害とは、目が見えない・見えにくいなど、視力や視野に関する障害のことです。1~6級があり、1級は「両目の視力の和が0.01以下のもの」と定められています。
視覚障害に認定される病気は、全盲や弱視のほか、視野狭窄(視野が狭い)、色覚障害(色が認識しづらい)などがあります。
また、視覚障害を引き起こす原因は、先天性白内障・未熟児網膜症・加齢黄斑変性・緑内障などさまざまです。
2.聴覚・平衡機能の障害
聴覚障害とは、耳が聞こえない・聞こえにくいといった、耳での聞き取りに関する障害です。中耳や外耳の疾患による「伝音性難聴」と、内耳や内耳に続く神経の疾患による「感音性難聴」、中耳と内耳の両方に原因を持つ「混合性難聴」があります。
検査器具を着ける位置や音の高さを変えて聞こえ具合を測り、結果をグラフ化した「聴力図」や、鼓膜の状態がどうかという診断などから、慎重に等級が判断されます。
また、平衡機能障害とは、耳や脳の機能に障害があり、起立や歩行などのバランスが取りづらいことです。ふらつきやめまいなどの症状があります。
障害の度合いに応じて、聴覚障害は2・3・4・6級、平衡機能の障害は3・5級に分けられます。
引用元:「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について|厚生労働省
3.音声・言語・そしゃく機能の障害
音声・言語障害とは、発声に関して支障がある状態です。聴覚障害によって発話が難しい場合のほか、喉頭がない(無喉頭)・失語症などの原因があります。
また、そしゃく(咀嚼)機能障害は、食べ物を噛んだり飲み込んだり(嚥下=えんげ)することが困難である障害です。神経や筋肉が上手に働かない、怪我や病気で口や喉頭が機能しづらいなどの原因があります。
等級には3級と4級があり、3級は機能が喪失した状態、4級は著しい障害があるケースです。
▼関連記事
構音障害とはどんな障害?働きやすい環境や向いている仕事もチェック
失語症の症状や種類とは?仕事を探すときに使える支援サービスも紹介
吃音とは?症状や原因、大人が悩む働く上での工夫やサポートも解説
そしゃく機能障害の方と仕事|働きやすい環境や就職活動におすすめのサービスを解説
4.肢体不自由
肢体不自由とは、上肢・下肢・体幹(胴体)に欠損や障害があり、日常の動作に困難を抱えている状態です。
先天的な欠損や機能不全のために不自由を抱えている場合や、事故など後天的な原因で手足の一部が切断されている、または麻痺などにより、思い通りに動かすことができないなど、さまざまな症状があります。
義手・義足・車椅子で生活しているなどいろいろな状態の方がおり、日常生活にどの程度の支障をきたすと考えられるかによって等級が異なります。上肢・下肢障害は1~7級、体幹障害は1・2・3・5級のいずれかです。
▼関連記事
上肢障害の等級・制度を知る!労災認定や仕事探しについても解説
下肢障害の等級・制度を知る!労災認定や仕事探しについても解説
体幹機能障害の方が仕事上で感じやすい壁・就職先に求めたい配慮とは?求人例や就労支援サービスも紹介
5.内部障害
内部障害とは、体内にある臓器・器官に障害を抱えている状態です。細かく7つに分類されるので、それぞれの症状を解説していきましょう。
| 障害の種類 | 等級 |
| 心臓機能障害 | 1・3・4級 |
| じん臓機能障害 | 1・3・4級 |
| 呼吸器機能障害 | 1・3・4級 |
| ぼうこう・直腸の機能障害 | 1・3・4級 |
| 小腸機能障害 | 1・3・4級 |
| ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害 | 1~4級 |
| 肝臓機能障害 | 1~4級 |
1.心臓機能障害
心臓は、全身に血液を送るための重要な臓器です。心臓機能障害とは、心臓の機能が低下し、生活に支障がある状態をいいます。心臓発作・心不全などの心疾患によって生じることが多いです。
障害の度合いや状態によっては、ペースメーカー(胸部に埋め込む医療機器)や人工弁を装着しているケースもあります。
1・3・4級があり、1級は心臓の障害により自分の身の回りの生活が極度に制限されている状態です。
2.じん臓機能障害
腎盂炎(じんうえん)や腎硬化症などのじん臓(腎臓)に関する病気により、じん臓が正常に機能しない状態です。老廃物の排出がうまくいかない、高血圧、貧血、末梢神経症などの症状が見られます。
心臓機能障害と同じく、状態に応じて1・3・4級に分けられます。
3.呼吸器機能障害
通常、呼吸をするときは、鼻や口から吸った空気が気管を通って肺に届けられます。呼吸器障害とは、そのいずれかの器官の機能が低下することによって、息切れが起きたりうまく呼吸できなかったりすることです。
心臓やじん臓の障害と同様に、呼吸器機能障害も1・3・4級の等級に分けられます。
4.ぼうこう・直腸の機能障害
ぼうこう(膀胱)が機能することによる排尿、直腸が機能することによる排便など、排泄を適切に行えない状態です。排出させるために、ストマ(ストーマ)と呼ばれる、人工膀胱や人工肛門を造設することもあります。
ぼうこう・直腸の機能障害の等級も、同じく1・3・4級です。
5.小腸機能障害
小腸は、胃で消化した食べ物の栄養分を吸収する働きを持つ大切な器官です。小腸機能障害とは、疾患や切除によって小腸の機能が低下し、栄養がうまく摂取できない状態をいいます。
1・3・4級に分かれており、1級では推定エネルギー必要量の60%もの栄養剤を投与しなければなりません。3級や4級でも口にするものの制限が多く、周囲からの配慮が必要です。
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染して免疫力が低下した状態です。免疫不全の状態になると、「後天性免疫不全症候群(AIDS)」と呼ばれます。免疫力が不全・低下すると、わずかな菌にも感染しやすくなるため、体調管理に細心の注意を払わなければなりません。
HIVによる免疫機能障害は、生活への支障度合いに応じて1~4級に分けられます。1級は日常生活がほぼできない状態です。
7.肝臓機能障害
肝臓は、物質の解毒や胆汁の生成などの役割を担う器官です。肝臓機能障害とは、肝硬変・肝炎・肝臓がんなどによって機能が低下し、むくみ・黄疸・倦怠感などの症状が起きて生活に支障が出た状態のことをいいます。
他の内臓の障害とは異なり、HIVの障害と同じ1~4級に分けられます。
身体障害がある方の雇用・就労形態

身体障害を抱える人が仕事をする場合、3つの就労タイプがあります。自分の状態に適した職場や働き方を見つけるため、就職の際によく確認しましょう。
一般雇用(一般就労)
一般的な求人に対して、募集条件を満たしていれば応募できるものを「一般雇用(一般就労)」といいます。身体障害があったとしても、公表することは義務ではないため、伝えずに就職する「クローズ就労」も可能です。
障害者雇用
障害者雇用促進法に基づき、障害者のための採用枠を用意している企業も多いです。あらかじめ障害のことを伝えたうえで採用されるため、身体障害のある方でも働きやすい環境が整っていることが期待できます。
障害者雇用枠に応募するためには、身体障害者手帳が必要です。手帳を持ってから初めて就職・転職する場合などは、後述する支援サービスを利用しながら仕事を探してみてはいかがでしょうか。
引用元
障害者の雇用の促進等に関する法律 | e-Gov 法令検索
▼関連記事
障害者採用とは?一般採用との違いやメリット・デメリット、企業選びのポイントをわかりやすく解説!
障害者雇用にはどんな働き方がある?職種や利用できる支援制度、仕事をする上での悩み、成功事例を紹介
福祉的就労|就労継続支援(A型・B型)
「福祉的就労」とは、障害をお持ちで一般就労が難しい方が障害福祉サービスのサポートを受けながら働く方法です。対象には、就労継続支援A型・就労継続支援B型などがあります。
就労継続支援とは、障害により一般企業での就職が難しい人に対し、就労継続支援事業所において、働く場を提供したり知識・能力の訓練を行ったりする福祉サービスです。
雇用契約をして給料を支払う「A型」と、契約はせず作業量に応じて工賃が支払われる(成果報酬)「B型」の2タイプがあります。
引用元:障害者総合支援法
就労継続支援について詳しく知りたい方は、ぜひ以下のページもご覧ください。
就労継続支援A型・B型とは?特徴や違い、窓口や利用手続きの流れを解説
給料・賃金の目安
就労継続支援で働く場合の令和3年度の平均賃金は、A型で81,645円(時間額926円)、B型で16,507円(時間額233円)でした。前年度はA型79,625円、B型15,776円で、いずれも上昇しています。
また、この金額はあくまでも平均であり、働き方や所属する事業所によっても異なります。希望に応じて、より多くの収入を目指すことも十分可能です。
引用元:障害者の就労支援対策の状況
身体障害をお持ちの方が受けられる可能性があるサービス

世の中では、身体障害がある人が生活しやすいように、いろいろな社会福祉サービスや支援制度が用意されています。そこで、どんなものがあるのか例を挙げます。
なお、住んでいる自治体や障害の状態などによって支援内容が異なる場合もあるので、自治体の担当窓口で相談・確認してみてください。
障害年金
障害年金とは、障害によって生活や仕事に支障がある場合に受け取れる年金のことです。「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、受給するためには所定の要件を満たす必要があります。詳細は下記ページをご覧ください。
引用元:障害年金について
補装具の交付・貸与
ストーマ・義足・補聴器など、障害を補完して生活しやすくするための道具を、給付もしくは貸与してもらえるサービスです。修理が必要な場合、修理費用を助成してもらえることもあります。
医療費の助成
「心身障害者医療助成制度」により、精神や身体に障害をお持ちの方の医療費の一部を助成してもらえます。障害のために通院や入院をする機会が多い方もいらっしゃるので、費用の自己負担が減ると助かることでしょう。
ただし、助成を受けるためには障害者手帳が必要です。自治体によって内容が異なるので、お住まいの地域でどの程度の助成を受けられるか確認してみてください。
自立支援医療(更生医療)
障害をお持ちの方が自立した日常生活を送れるよう、障害の軽減や除去を目的とした手術などの治療を受けた際に、医療費の一部を負担してもらえる制度です。
経済的な問題でなかなか治療を受けられなかった方も、制度を利用することによって、高額な治療費や継続的な医療費の支払いの負担を抑えられるでしょう。
さまざまな割引・控除
電車やバスなどの公共交通機関の運賃・レジャー施設や博物館などの入場料・公共料金や税金などが、通常より安い、または無料になることもあります。
通院などで公共交通機関をよく利用する方や、さまざまな支払いに頭を悩ませている方などにとって、このような割引や控除は侮れません。少しでも暮らしやすくなるように、受けられる支援は積極的に受けるとよいでしょう。
身体障害をお持ちの方の就職・転職活動をサポートしてくれるサービス

つづいて、仕事探しの際に相談に乗ってくれ、活動を支援してくれる機関やサービスを紹介します。一人での就職・転職活動が不安な方は、サポートを受けながら適切な環境を探すとよいでしょう。
ハローワーク
ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。窓口や施設に設置してある検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。
ハローワークには専門援助部門が設けられており、窓口には専門の相談員が配置され、障害をお持ちの方が就職活動をするための支援を行っています。
一般向けの求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗ってくれ、障害のある方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害をお持ちの方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。全都道府県に最低1カ所ずつ以上設置することが義務付けられています。
センターでは、直接就職先を紹介するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携しながら、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといった支援を実施しています。
障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。
引用元
障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、トレーニングと就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。
利用者にとって、事業所に通いながら就職に必要な知識や技術を獲得でき、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。
全国に3,300カ所以上あり、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障害をお持ちの方の仕事面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などと呼ばれることもあります。
なかぽつは、全国に337カ所(令和5年8月22日時点)設置されています。社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。
障害をお持ちの方への就職支援や助言のほか、事業所に対して障害者雇用に関する助言を行ったり、関係機関との連絡調整を実施したりしています。
引用元
障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省
令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧 (計 337センター)|厚生労働省
障害者向け転職エージェント
障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化した、転職エージェントもぜひ利用してください。
障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。
高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。
就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。
身体障害の種類や状態に応じた働き方を見つけよう

「身体障害」と一言でいっても、障害の発生する部位は、視覚・聴覚・発声・肢体・臓器と多岐にわたります。困難を感じる部分や程度には個人差があるため、一人一人の状況に合った生活や仕事をして、充実した日々を送りましょう。
就職を目指す方も、体に無理のない範囲で働くことが大切です。どんな仕事をしたいか、どのような形態で働くかなどに悩んでいるなら、ぜひDIエージェントにご相談ください。お一人お一人の状況を確認しながら、適切な働き方をご提案させていただきます。
関連記事はこちら:
「就職・転職活動は検討しているけど、エージェントって何?」という方に向けて、エージェントの特徴や利用方法について解説しています。
障害者枠では転職エージェントを利用すべき?メリット・注意点を含め解説!
社会福祉士。福祉系大学を卒業し、大手小売店にて障害者雇用のマネジメント業務に携わる。その後経験を活かし(株)D&Iに入社。キャリアアドバイザーを務めたのち、就労移行支援事業所「ワークイズ」にて職業指導・生活支援をおこなう。