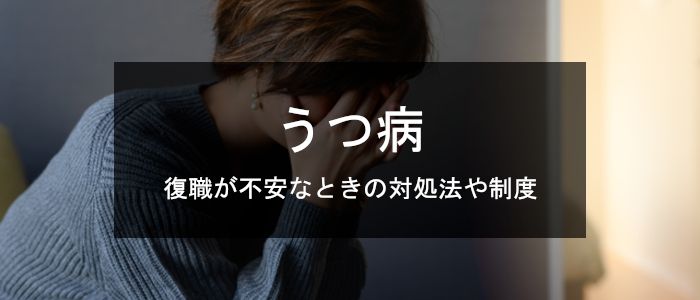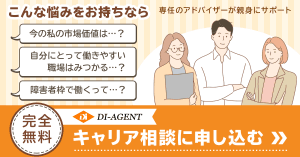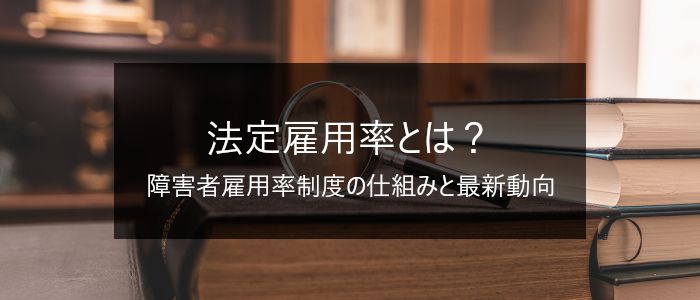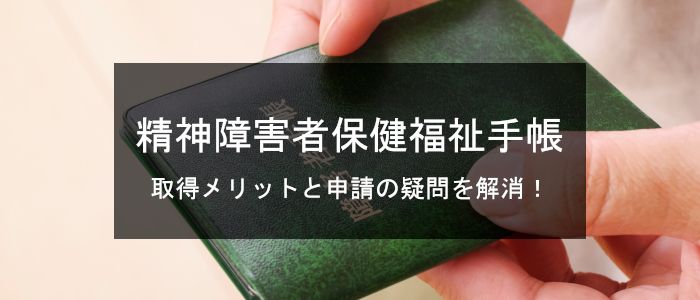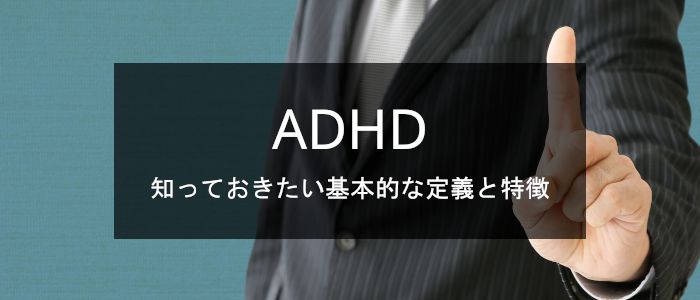うつ病で休職すると、復職するのが怖いと不安を感じる方もいます。では、不安になった場合はどのように対処すればいいのでしょうか。少しでも気持ちを和らげるために、対処法を知っておくと安心です。
また、急な復職が心配な場合に利用できる制度についても解説します。うつ病のような精神疾患では、無理をせず自分の体を優先することが重要です。この記事が現在不安を抱えている方のお役に立てれば幸いです。
うつ病の発症から復職するまでの流れ

はじめに、うつ病を発症してから休職を経て復職するまでの流れを見ていきましょう。
1. うつ病発症
何に対しても気力がわかない・仕事に行きたくない・眠れなくて体がだるいなど、うつ病のような症状が出たら、医療機関を受診しましょう。休職や退職を考えている場合、医師から正式な診断書をもらう必要があります。
2. 休職して療養する
診断書をもらったら、会社で休職届を出すなどの必要な手続きを行って休職しましょう。休んでいる間はなるべく仕事のことは考えず、静養に努めてください。
3. 復職への相談をする
うつ病の症状が落ち着いてきた頃に、医師や職場に復職について相談しましょう。仕事復帰への意欲があるか、日常生活が問題なく送れているか、きちんと通院して必要な治療を受けているかなどの点が重要なチェックポイントです。
主治医からのOKが出なければ時期尚早かもしれません。復職してもよいという判断をもらえれば、いつからどのような形で仕事を再開するのか、職場と調整を行います。
4. 復職に向けて準備する
休職中は生活習慣が乱れがち。寝る時間や起きる時間が仕事のリズムに合っていない・食生活が整っていない・身だしなみを気にせず寝間着のまま1日過ごすなどの傾向が見られます。
体調が悪い間は体を優先すべきですが、復職が決まったら、仕事に復帰するまでに、乱れた生活習慣を規則正しい状態に整えることが大事です。
特に睡眠は乱れる傾向があるので、起床時間と就寝時間を仕事をしているときの時間に戻しましょう。体力の回復を目指し、適度な運動を取り入れるのもよいでしょう。
5. 復職する
担当医師に復職診断書を書いてもらい、職場の許可が下りれば、いよいよ仕事に復帰です。久しぶりの出勤では緊張や不安を感じる方も多いため、次章で対処法を解説します。
復職するのが怖い・不安というときの対処法

うつ病で休職していると、「職場の人に何か噂されているのでは」「本当に復帰できてちゃんと働けるんだろうか」「再発したらどうしよう」など、復職が怖くなり不安な気持ちを抱える方も多いです。そのようなときにどうすればいいのか、対処法を解説します。
人に相談する
不安や恐怖は、人に話すことで落ち着く傾向があります。家族や友達などの相談相手を見つけて、今の気持ちを吐き出しましょう。どうしても周りの人に言いづらい場合は、医師やカウンセラーがいるような相談窓口などでもよいでしょう。
焦らずしっかり休む
うつ病になる方は、真面目で勤勉な方が多いです。休職していると、「早く復帰しないと職場の人たちに迷惑をかける」という焦燥感を感じがちですが、焦りはストレスにつながり、うつ病のような疾患では逆効果になりかねません。
特に強い症状がある間は、仕事のことは考えず、療養することだけに意識を向けましょう。
ストレスコーピングを行う
不安な点や仕事で負担だったことなど、ストレスの原因と考えられる要素を書き出し、どんな面がストレスだったかを明確にした上でさまざまな対策方法を考える「ストレスコーピング」もおすすめです。
自分に合った対策をなるべく多く考えておくことで、事前の備えもしやすくなります。
生活習慣を整えて適度な運動をする
前述にもありますが、乱れた生活を戻したり、適度に体を動かしたりすることも重要です。症状がひどいときは難しいですが、生活習慣の乱れもうつ病にとって良くない要素。健康的に復職するためにも、生活リズムを正しましょう。
また、休職中は家にこもりがちで運動不足になりやすいです。ストレッチや軽いウォーキングなどからでいいので運動を始め、体力を取り戻してください。
通院・治療を続ける
復職できるほど回復してくると、病院から足が遠のいてしまう方もいます。しかし、医師の指示に従って治療を継続することも大切です。
うつ病には体調のいいときと悪いときの波があり、波を繰り返しながら回復に向かっていくため、不安なときは体調が良くない可能性も。自己判断で通院をやめることは控えましょう。
今の仕事について考え直す
業務量・業務内容・勤務時間など、今の仕事のままで本当にいいのかを見つめ直すことも重要です。同じ職場に戻る場合でも、体調によっては部署を変えてもらったり、時短勤務やテレワークをさせてもらったりしたほうがいいかもしれません。
復職が不安な場合に利用したい制度

復職に対して怖い・不安だという気持ちが強い場合、いくつかの制度を利用できることもあります。ぜひ活用してみてください。
試し出勤・慣らし出勤
職場によっては、試し出勤(慣らし出勤)制度が整っていることがあります。本格的な復帰ができるかどうかを確認するための制度です。
一定の期間、時短で簡易的な業務を行う方法や、就業時と同じ時間を図書館などで過ごす方法、通勤経路を往復する方法などさまざまなやり方があります。職場に相談し、制度があればぜひ利用しましょう。
リワークプログラム
「リワークプログラム(復職支援プログラム)」でリハビリをしてから復職する方法もあります。個人作業課題・キャリアデザイン・ソーシャルスキルトレーニングなどの内容があり、実施している機関によって特徴が異なるため、下記で紹介します。
企業|職場リワーク
自社の休職者を対象に、独自のリワークプログラムを行っている企業があります。内容は企業ごとに異なりますが、社員が復職後に安定して働けるかどうかを見極めるのが目的です。
リワークのほか、本格復帰に向けたプランを組んでもらえるケースもあり、徐々に仕事の勘を取り戻しながら復職できるでしょう。
引用元
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き|厚生労働省
医療機関|医療リワーク
医師や看護師などの専門スタッフが「医学的リハビリテーション」を行う方法です。心身機能を回復・安定させ、再び休職することを防止するためのサポートを実施しています。費用はかかりますが、健康保険を適用できるため、一部の自己負担で済むことが特徴です。
地域障害者職業センター|職リハリワーク
各都道府県に設置されている「地域障害者職業センター」でも、復職のための支援が行われています。センターに所属する職業カウンセラーが、休職者や企業に対して復職のサポートを実施するものです。
職場からの提案によって職リハリワークを受けられるケースも。医療機関との連携もしており、休職者・職場・医師の三者の合意に基づいて復職を目指せることが特徴です。
うつ病からの復職にあたっての注意点

うつ病を乗り越えて復職する際、不安になるのはやむを得ません。復帰にあたっては、以下の点に注意しましょう。
- 焦らない
- 体調管理を行い治療を続ける
- 無理をしたり抱え込んだりしない
復職しても、最初から以前と変わらない状態で働けるとは限りません。思ったより作業に時間がかかってしまったり、うまく進められなかったりすることもあるでしょう。しかし、焦らず、無理をせず、自分の体調と相談しながら働くことが大切です。
うつ病休職後に転職するときに相談できる支援機関

うつ病で休職したのち、復職ではなく転職する場合は、相談に乗ってくれ、仕事探しをサポートしてくれるサービスを利用するのがおすすめです。プロの手を借りながら、自分に合った職場を見つけましょう。
ハローワーク
ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。窓口や施設に設置してある検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。
ハローワークには専門援助部門が設けられており、窓口には専門の相談員が配置され、障害をお持ちの方が就職活動をするための支援を行っています。
一般向けの求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗ってくれ、障害のある方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害をお持ちの方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。全都道府県に最低1カ所ずつ以上設置することが義務付けられています。
センターでは、直接就職先を紹介するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携しながら、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといった支援を実施しています。
障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。
引用元
障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、トレーニングと就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。
利用者にとって、事業所に通いながら就職に必要な知識や技術を獲得でき、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。
全国に3,300カ所以上あり、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障害をお持ちの方の仕事面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などと呼ばれることもあります。
なかぽつは、全国に337カ所(令和5年8月22日時点)設置されています。社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。
障害をお持ちの方への就職支援や助言のほか、事業所に対して障害者雇用に関する助言を行ったり、関係機関との連絡調整を実施したりしています。
引用元
障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省
令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧 (計 337センター)|厚生労働省
障害者向け転職エージェント
障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化した、転職エージェントもぜひ利用してください。
障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。
高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。
就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。
うつ病からの復職が怖いときは対策を取り、場合によっては転職を検討しよう

うつ病からの職場復帰は恐怖や不安がつきものです。しかし、対策によってネガティブな感情を軽減できる可能性もあります。どうしても復職が困難なときは、もっと自分に合った環境に転職するのもよいでしょう。
障害をお持ちの方向けの就職支援を行っているDIエージェントでは、スキル・ご希望に合う求人の紹介や、仕事探しの助言などのサポートを実施しています。転職はまだ検討段階という方も、ぜひ気軽にお問い合わせください。
▼関連記事
・障害者採用枠で働くことについて、メリット・デメリットを解説しています。これから就職・転職を検討されている方はぜひご一読ください。
障害者採用とは?一般採用との違いやメリット・デメリット、企業選びのポイントをわかりやすく解説!
・「就職・転職活動は検討しているけど、エージェントって何?」という方に向けて、エージェントの特徴や利用方法について解説しています。
障害者枠では転職エージェントを利用すべき?メリット・注意点を含め解説!

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。