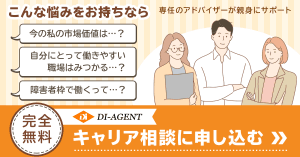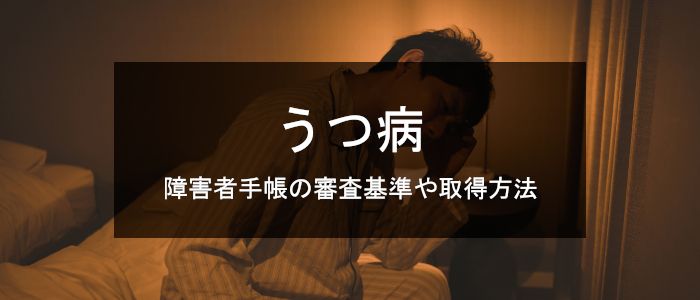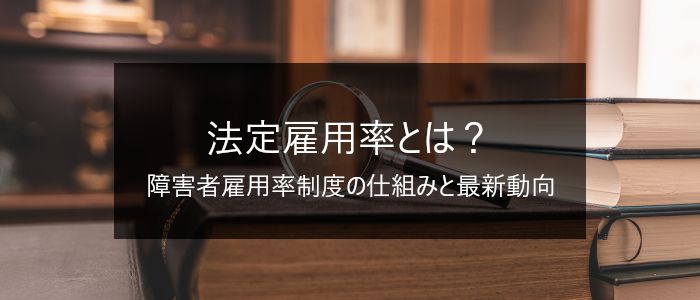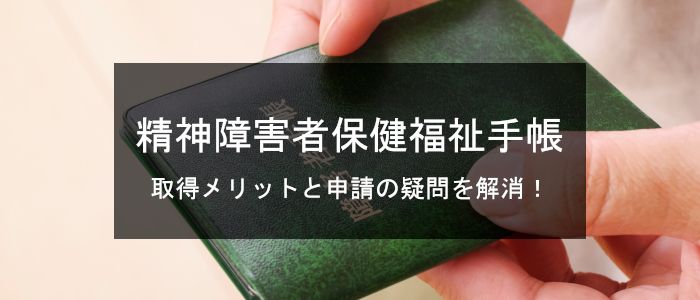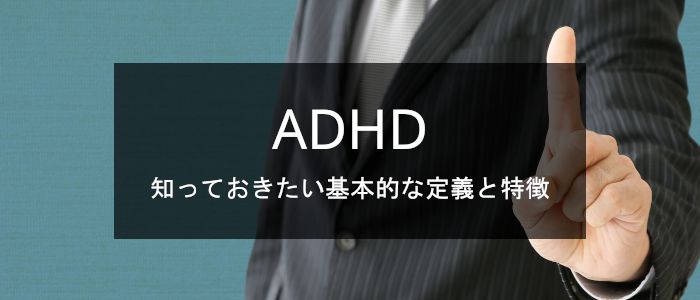「どうしても仕事に行けない」、「働けない自分はダメな人間なのではないか」、「収入がなくなって生活していけるのだろうか」うつ病による休職は、こうした不安や自責の念に苛まれやすいものです。
厚生労働省の統計によると、うつ病などの気分障害の総患者数は約127万人に上ります。働き盛りの年代でも多く発症する病気であり、誰にでも起こりうるのです。
うつ状態に陥ったとき、大切なのは無理に頑張りすぎないことです。利用できる支援制度をしっかりと活用しながら、回復に向けてまずはゆっくりと休息を取りましょう。
そこで本記事では、うつ病で働けない状況になったときに利用できる様々な支援制度や、復職に向けたステップを詳しく解説します。経済的な心配を少しでも軽減し、あなたが心身の回復に専念できる環境づくりをサポートできれば幸いです。
うつ病で働けないときに利用できる経済支援制度

うつ病で働けない状況になると、収入が途絶えることへの不安が大きくなります。しかし、日本には充実した社会保障制度があり、様々な経済的支援を受けることができます。ここでは、利用可能な制度を収入・生活費の支援と医療費の支援に分けて紹介します。
収入や生活費を支援する制度
収入や生活費を支援する制度には、以下のようなものがあります。申請先や支給額を表にまとめましたので、参考にしてください。
| 制度名 | 対象者 | 支給額(目安) | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険に加入している会社員、公務員 | 標準報酬日額の2/3 | 全国健康保険協会支部 |
| 労災保険制度 | 業務が原因の場合 | 給付基礎日額の80% | 労働基準監督署もしくはハローワーク |
| 雇用保険(失業保険・失業手当) | 退職者 | 離職時賃金の45-80% | ハローワーク |
| 生活保護制度 | 低所得者 | 地域により異なる | 市区町村の福祉事務所 |
| 特別障害者手当 | 20歳以上の重度障害者 | 月額28,840円 | 市区町村の窓口 |
| 障害年金 | 一定の障害状態の方 | 等級により異なる | 年金事務所 |
| 特別障害給付金制度 | 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方 | 1級:55,350円 2級:44,280円 | 年金事務所 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得者・障害者世帯等 | 資金種類により異なる | 市区町村社会福祉協議会 |
それぞれの制度について、詳しく説明していきます。
傷病手当金
傷病手当金は、会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった場合に、休業中の所得を補償する制度です。
業務外の病気やケガで連続する3日間を含み4日以上休職し、休職により給与の支払いがない場合に受給できます。
支給期間は最長1年6ヶ月までで、支給額は直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の3分の2となります。申請には医師の意見書と会社の証明が必要で、定期的な更新手続きが求められます。
労災保険制度
業務や通勤が原因でうつ病を発症した場合、労災保険の対象となります。認定には、業務による強い心理的負荷の存在や、業務以外に明確な原因がないこと、発症前おおむね6ヶ月間に強い心理的負荷を伴う出来事があったことなどが条件となります。
給付内容には、給付基礎日額の80%が支給される休業補償給付のほか、治療費全額の医療補償や通勤費用の支給が含まれます。
雇用保険(失業保険、失業手当)
雇用保険は失業保険や失業手当のような通称でも知られ、会社を退職した場合、一定期間の給付を受けることができます。
受給には離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。自己都合退職の場合は給付開始まで3ヶ月の待機期間がありますが、うつ病などの理由で退職した場合は、すぐに給付されるケースもあります。
基本手当日額は離職時賃金の45-80%で、給付日数は年齢や離職理由により90~360日の範囲で決定されます。
引用元
基本手当について
生活保護制度
他の制度を利用してもなお生活が困難な場合のセーフティーネットとして、生活保護制度があります。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活が困窮している場合で、親族など扶養義務者による扶養が受けられない場合に申請が可能です。生活扶助、住宅扶助、医療扶助などが支給され、その金額は地域や世帯構成によって決定されます。
引用元
生活保護制度|厚生労働省
特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方が対象となる制度です。
重度の障害により日常生活に常時特別な介護が必要で、所得制限の範囲内である場合に受給できます。令和6年度の月額支給額は28,840円です。
障害厚生年金
うつ病により長期的に就労が困難な場合、障害年金を受給できる可能性があります。障害の程度によって1級から3級まで区分され、それぞれ基本年金額の1.25倍、1倍、0.75倍が支給されます。
申請には障害年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などの書類が必要です。
引用元
障害年金|日本年金機構
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
特別障害給付金制度
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者の方を対象とした制度です。
学生や専業主婦であった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方が対象となります。令和6年度の給付額は1級が月額55,350円、2級が月額44,280円となっています。
生活福祉資金貸付制度
低所得者や障害者世帯などを対象とした貸付制度です。医療費や生活費の支払い、就職や技能習得のための費用など、様々な用途に応じた資金を低金利または無利子で借りることができます。
貸付限度額や返済期間は資金の種類によって異なり、民生委員による相談支援も受けられます。
医療費を支援する制度
医療費の負担を軽減するための制度として、以下のようなものがあります。
| 制度名 | 対象者 | 自己負担 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 自立支援医療制度 | 精神通院医療、更生医療、育成医療を受けている方 | 原則1割 | 市区町村窓口 |
| 心身障害者医療費助成 | 障害者手帳所持者 | 地域により異なる | 市区町村窓口 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 重度障害者 | 地域により異なる | 市区町村窓口 |
自立支援医療制度
精神障害で通院による治療を受ける場合、医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神通院医療、指定医療機関での治療、薬局での調剤が対象となり、原則医療費の1割の自己負担で医療を受けることができます。所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。
心身障害者医療費助成制度
精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となる医療費助成制度です。保険診療の自己負担分が助成され、入院・通院ともに対象となります。
ただし、助成内容は地域によって異なるため、居住地の自治体に確認が必要です。
重度心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度と同様に、精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となる医療費助成制度です。保険診療の自己負担分が助成され、入院・通院ともに対象となります。
自治体によって助成内容が異なり、心身障害者医療費助成制度と同様の内容であるケースもあります。
うつで働けない人が利用できる4つの支援機関

うつ病で働けない状況にある方を支援する専門機関について説明します。これらの機関では、医療・生活・就労の各面からサポートを受けることができます。
就労移行支援事業所
就労を目指す障害者に対して、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行う施設です。就労に必要な基礎能力の形成から、職場探し、職場定着までの一貫した支援を受けることができます。
利用を希望する場合は、まず市区町村の窓口に相談し、障害福祉サービスの申請を行います。その後、施設見学や体験利用を経て、本格的な利用開始となります。
精神保健福祉センター
精神保健福祉に関する専門的な相談や技術指導を行う機関です。こころの健康相談や社会復帰相談、家族教室の開催、普及啓発活動など、幅広いサービスを提供しています。
専門家による相談を無料で受けることができ、必要に応じて適切な医療機関や支援機関の紹介も行っています。
障害者就業・生活支援センター
障害者の就業面と生活面の一体的な支援を行う機関です。就業に関する相談支援や障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言のほか、生活習慣の形成・健康管理の支援、地域の支援機関との連絡調整なども行っています。就職後の職場定着支援も重要な役割となっています。
うつで働けない状態から復職するためのステップ

復職に向けては、段階的なアプローチが重要です。まずは十分な休養と治療から始め、主治医の指導に従いながら適切な治療を受けることが基本となります。規則正しい生活リズムを整え、睡眠・食事・運動の基本的な生活習慣を整えていくことが求められます。
次のステップとして、リワークプログラムへの参加が推奨されます。このプログラムでは、職場復帰のための準備を行い、生活リズムの改善や対人関係能力の向上、職場での課題への対処方法を学ぶことができます。
その後、段階的な職場復帰を進めていきます。主治医と相談の上で復職時期を決定し、産業医との面談を経て、試し出勤制度の利用や短時間勤務からスタートするなど、徐々に勤務時間を延ばしていく方法が一般的です。
また、職場環境の見直しも重要なステップとなります。業務内容の調整や勤務時間の配慮、必要に応じた配置転換などを検討します。場合によっては、新しい職場への転職を考えることも選択肢の一つとなります。
うつで働けないときには無理をせず制度を活用して休養しよう

うつ病からの回復には、適切な治療と十分な休養が不可欠です。本記事で紹介した様々な支援制度を活用することで、経済的な不安を軽減し、心身の回復に専念することができます。
必要な場合は、医療機関や支援機関に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。一人で抱え込まず、利用できる支援を最大限に活用しながら、回復への道を歩んでいきましょう。
なお、現在の職場環境が回復の妨げとなっている場合は、転職という選択肢も視野に入れることが大切です。その際は、障害者雇用に理解のある企業への転職をサポートする専門的な転職エージェントの利用も検討してみてください。
▼関連記事
・うつ病でも今の仕事を続けたいと考えている場合は、まずは休職のタイミングや方法について知っておくことが大切です。
うつ病でも仕事は続けられる?克服する方法や休職するタイミングを解説
・休職する前に必要な手続きや貰える手当をさらに詳しく知っておくことで、安心してお休みができます。
うつ病で仕事を休職するには診断書が必要!手続きや休職期間、もらえる手当、復職について知ろう
・うつ病から回復して次の仕事を考えはじめたら、まずは転職のポイントを押さえましょう。
うつ病になったら再就職は難しい?転職活動のポイントや向いている仕事を知ろう

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。